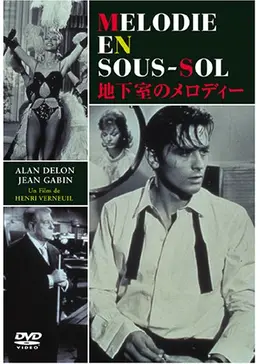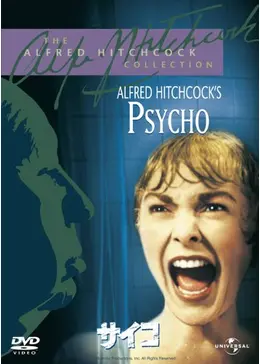11月3日付読売新聞に台湾の総統選について興味ある報道があった。今まで、全く興味はなかったのだがこの話は非常に面白いと思った。既存の政党間でのせめぎあいの中で、突然登場した柯文哲という人の話である。
同氏は今や台湾を混乱させつつある中国との関係について、中国との統一論も台湾独立の議論も、議論するだけ無駄だ、という。いわく、米国は中国と台湾の統一を許さず、中国は台湾の独立を許さないという現実は、解決の方法もない議論だ。解決のできない問題に30年も議論している方がおかしい。いまの台湾、という現状をそのまま認めればいいではないか、と主張するのである。詳しいことはわからないが、現在の台湾は平和だし、経済も順調、半導体の分野にあっては一方の雄として君臨している。この現状で何が悪いのか、という極めて単純な理屈である。このことは小生にすんなり納得できる。
同じ日、違う紙面に 変容する米国 というシリーズの3回目があって、ここでは不法移民の激増で混乱している米国の現状の報告があった。見出しが 揺らぐ寛容 とあるのがその深刻さを物語っている。トランプの有名な メキシコとの壁 でこの問題の異常さがクローズアップされたが、その後バイデン政権になって見直しがあり、またぞろ膨大な数の不法入国が後を絶たない。国境沿いのテキサスやアリゾナは彼らをまとめてバスに乗せ、内陸部の大都市へ放り出す、という乱暴な対策に出ている。この結果、ニューヨークやシカゴではシェルターが足りず、対策に巨額な費用が掛かり、犯罪が急増し、職を奪われる人が増加する、という結果となって 街が壊れる という危機意識が醸成されつつあるようだ。いうまでもなく米国は移民によってつくられた国であり、欧州各国にくらべればこういう事態にもいわば国是として寛容さを保ってきたわけだが、このままで推移すれば、米国の人口の最大のパイはヒスパニック系になると予想されるとなれば、もうその寛容も限界に近付きつつあるというのが実態なようだ。
かたや欧州ではアフリカや中近東からの移民、とくにアラブ人の入国が増え続けているが、この内陸部の国々が抱える問題を考えてみると、米国も欧州も他国と地続きであり、人間の移動を阻むことが困難な一方、ひとたび入国し定着すればことなる一神教のせめぎあいという問題を避けられない。これに対し、台湾は大陸と海によって隔てられ、温和な国民性と単一文化をはぐくんできたといういわば地政学的な差がある。そしてそのことはそっくり日本にも当てはまる。同じ漢字文化の国とは言え、韓国は大陸と地続きの半島国家であり、事情は異なってくるだろう。
先日、イスラエルの事情についての議論の中で、現在起きている戦争状態のなかで日本はどうするか、という課題について触れたが、その中で我が国の地政学・物理的な位置、単一民族単一文化、実質的に無宗教、などという、この意味では現在苦悩している大陸国家に比べて有利にはたらく天与の優位性を生かして、現実を素直に受け入れた、現実に即した国策ということを考えるべきだと書いた。硬派(?)の船津於菟彦なんかからは おめえ、何言ってんだ、と怒られたが、どんなものだろうか。






 ファイサル1世と写真に写るロレンス(右から2人目):
ファイサル1世と写真に写るロレンス(右から2人目):