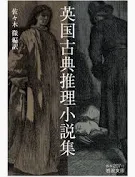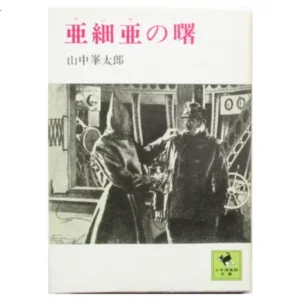英国古典推理小説集 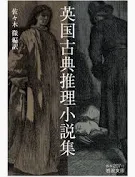 「英国古典推理小説集」(編訳者:佐々木 徹。発行:岩波文庫、2024年)を読む。久し振りの探偵小説だ(最近のミステリーと言う言葉に抵抗感があるのは歳を取ったせいなのか)。
「英国古典推理小説集」(編訳者:佐々木 徹。発行:岩波文庫、2024年)を読む。久し振りの探偵小説だ(最近のミステリーと言う言葉に抵抗感があるのは歳を取ったせいなのか)。
その内容は、題名に「小説集」とあるように、以下の短編六つ、長編一つ「ノッティングヒルの謎」、及び、長編の一部とその評価から成り立っている。
先ず、イチャモンから始める。ここでは、題名に古典と銘打っているが(確かに、小生が知っている作家は、ディケンズ、コリンズ、チェスタトンの3人だけだ)、古典とは、その評価が定まったものの事を言うのであって、ここに掲げられた短長編の殆どは、19世紀に発行されたいささかながら稚拙なものが多く、むしろ英国初期推理小説と見做すべきではないのか、「イズリアル・ガウの名誉」、「オッターモールの手」の二つは別にして。何故なら、例えば、「オッターモール氏の手」は、1929年に出版されたが、その9年前の1920年には、A.クリスティーの処女作「スタイルズ荘の怪事件」、F.W.クロフツの処女作「樽」が発行された年であり、正に英国本格探偵小説の黄金時代を謳歌していた時代と重なっているからだ。つまり、「イズリアル・・・」も同様だが、編者が、大変、気に入った20世紀の作品を何とか無理やりにここに捻じ込んだとしか思えない。
ここで、その一々に感想を述べる余裕はないので、以下、三つの作品に絞ることにする。
チャールズ・ディケンズ:バーナビー・ラッジ(1841年)の一部/エドガー・アラン・ポーの書評(1842年)。ポーが、「バーナビー・ラッジ」雑誌連載の途中まで読んで、その先を推測したのだが、物の見事に外してしまった。が、ポーは逆にディケンズの方が間違っている旨を指摘する書評だったようなのだが、これは正直に言って、ポーが何を言っているのか良く分からなかった。そこで、探偵小説の元祖とも言われるポーの「モルグ街の殺人」(蛇足だが、モルグとは死体安置所のこと)について一言。殺人、探偵、論理的な解決などと正当な探偵小説の筋道は通っているのだが、その犯人像が全く頂けない代物なのだ。何と、人間ではなく、オランウータン。蛇足だが、一寸、驚いたことに、ネットでは、犯人をバラシている。いくら良く仕込まれたオランウータンであっても、背後で操る人間の思う通りに動くものなのか。以後、小生、寡聞にして動物が犯人だと言う探偵小説には一度としてお目に掛かったことはない。つまり、これは現実的ではないと言うことだろう。と言うことで、小生、偉そうな言い方なのだが、この「モルグ街の殺人」を全く評価していない。
それに引き換え、「オッターモール氏の手」は、英国探偵小説の黄金時代の作品だけあって、久し振りにその面白さを満喫した。歯切れの良い文章と、それに伴った、スリルとサスペンス、意外な犯人像(ここでも、ネットでは犯人をバラシているが、これはマナーに反する)。確かに、本格とは言えないが、流石に、目利きでもある作家、E.クイーンは、この作品を短編の世界ベスト10の一つに選んでいる。
最後に、「ノッティングヒルの謎」だが、確かに、各種の資料を駆使するなど工夫を凝らしている。そして、最後の頁で、編者が親切にも、参考のため関係系図とか略年表を掲載してくれている(逆に言えば、それだけ複雑である証拠)。とは言え、それにしても、人間関係が余りにも複雑すぎて、小生の手に余る。もっと簡潔な話しに出来なかったのか。
と言う具合で、かねてから「オッターモール氏の手」と言う題名は知っていたが、実際に読んでみて、その出来具合の良さには感嘆の声を挙げた。バークは、1886年、ロンドン生まれで、1945年、逝去。どうやら短編を専門としており、それも真面なものではなく怪奇小説の類いのようだ。ネットで調べたところ、この他に二三、日本語に訳された作品があるようなので、追々、図書館から借りて来ることにしよう(原書を読む気なら、アマゾンで見つかるだろうが、情けないかな、その気力は、最早、完全に失せてしまった)。
チャールズ・ディケンズ:バーナビー・ラッジ(1841年)の一部/エドガー・アラン・ポーの書評(1842年)。
ウォーターズ:有罪か無罪か(1849年)
ヘンリー・ウッド夫人:七番の謎(1877年)
ウィルキー・コリンズ:誰がゼピディーを殺したか(1880年)
キャサリン・ルイーザ・パーキス:引き裂かれた短剣(1893年)
G.K.チェスタトン:イズリアル・ガウの名誉(1911年)
トマス・バーク:オッターモゥル氏の手(1929年)
チャールズ・フィーリクス:ノッティング・ヒルの謎(1862年)
(編集子)いまさらながら、わが友スガチューの読書にかける熱意と馬力に感服するし、選択眼は小生ごときの及ぶところではないが、少しばかりのつけたしを許してもらいたい。
本稿の中で、犯人が人間でない結末については小生も同意見だ。ただドイルのホームズもので、確か 四つの署名 だったと思うがマングースが出てくるものもあり、ノックス(だったと思うがダインかもしれない)が提唱した、かの推理小説20則ルールにも反している。しかしこのルールは推理小説というジャンルが確定してからの話なので、たとえばクリスティの代表作 アクロイド殺人事件 も違反している、ということになってしまうため、いささか腑に落ちないむきもあるようだ。 ミステリという定義についてスガチューが抱く違和感は、ハードボイルド、という呼称に小生が持つものと同じなように思う。HBの定義にはそれなりの理屈があるのであって、昨今の、特に我が国でHBと称する作品の多くは、単なる暴力場面の羅列であり、その道での代表とされる大藪晴彦の作品のほとんどは(処女作の 野獣死すべし は除くが)単なるガンマニアの妄想の羅列に過ぎない。その意味では数年前の原寮の急逝はまことに残念至極でならない。最近はバイオレンス小説、なる呼称も使われるようになったが、おそらく、これに含まれる大半がこの似非HBであって、スガチューが言おうとしているのも、昨今のミステリ、なるものが実は推理小説とは違ったものになっている、ということなのだろう。なお、ポケットブックにも最近のものは mystery ではなく thriller と書かれているものが多い。世界の大勢なのかもしれないし、SNSプラス大衆社会現象の表れかもしれないが、好ましいことではあるまい。
 本稿でスガチューが触れているクリスティのデビュー作 スタイルズの怪事件 はちょうど昨晩、読了。今日からクイーンに戻って、国名シリーズの最後、フランス白粉の謎 にかかったところだ。大塚文雄にあやぶまれながらポケットブック乱読第二章の始まりはハードボイルドから一転して、推理小説(日本中にはびこるミステリでなく)の創成期の作品から始めたところだ。こっちも意地を張ってスガチューに挑戦しよう。もっとも、先々月の白内障手術のアフタケアが終わり、読書用の眼鏡が出来上がるまではペースもあがらないのだが。
本稿でスガチューが触れているクリスティのデビュー作 スタイルズの怪事件 はちょうど昨晩、読了。今日からクイーンに戻って、国名シリーズの最後、フランス白粉の謎 にかかったところだ。大塚文雄にあやぶまれながらポケットブック乱読第二章の始まりはハードボイルドから一転して、推理小説(日本中にはびこるミステリでなく)の創成期の作品から始めたところだ。こっちも意地を張ってスガチューに挑戦しよう。もっとも、先々月の白内障手術のアフタケアが終わり、読書用の眼鏡が出来上がるまではペースもあがらないのだが。
 1927(昭和2)年は、年賀状を控えるなど異例の年明けで始ま
1927(昭和2)年は、年賀状を控えるなど異例の年明けで始ま