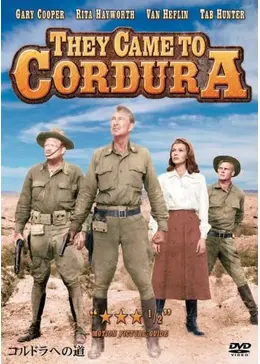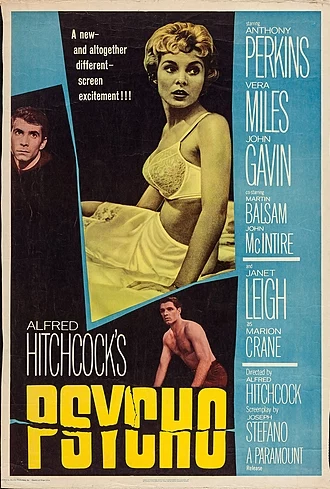ビッグモーターの呆れた実態につづいて、ここのところ、大企業の違法行為のニューズが続いているが、そのたびに出てくるのが 企業の ”ガバナンス” の問題、とか、欠如、といった議論である。明らかに誰が考えても違法であり、犯罪ですらあるビッグモーターのことと、ほかの事件を一緒にするのは無理筋だと思うのだが、いずれにせよ、一般に理解できる用語で言えば、要は監督不行き届き、であろう。組織が大きくなればどうしても目の行き届かない部分が生じてくるということは納得しないまでもある程度同情する部分もあるし、会社時代、管理職の端くれであった自分のことを考えても忸怩たるものはある。しかし組織全体が、管理職の眼を離れても、いわば自然体で、整然として機能するという事があれば話は違ってくる。
編集子は現在の日本ヒューレット・パッカードの前身、横河HP(YHP)に入社し、その立ち上がり時期に居合わせた。残念ながら発足当時には不況と相まって苦境が続き、米国本社から何人かのベテランが日本に駐在して支援をするという合弁企業にはよくある構図のもとで、生産管理課という部署にいた頃の話である。いろいろな経営指標の中で、部品材料の在庫管理、ということが非常に厳格に監視されていたこともあって、数量管理は当然として購入価格の管理が大変だった。当時はまだ日本のメーカーの品質には問題があったし、価格も割高であったが、ある業者から、大幅な割引の話が持ち込まれたことがある。その部品についてはこの会社のライバル企業が既存の取引先だったから、それを覆す目的であることは明白で、当時の日本の業界ではよくある話だった。担当者としてはありがたい話だったが、上司にあたるアメリカ人は、その取引を容認しなかった。こちらが悪いことをしているわけではないし、どうも納得がいかない。なにか誤解でもあるのか、という事もあって、Why ? と問いただしたところ、その男が私の顔を厳しい顔つきで見つめながらこう言ったものだ。
Because that is not the way we do business at HP
(HPではそういうやり方でビジネスはしないからだ)
当時、HPでは製品の販売にあたって絶対に値引きを許さなかった。特にHPが切り込もうとしていた電子測定器という分野では、ライバル間の値引き競争が激烈だったのだが、あくまで製品の機能と客先に対する貢献の成果がHPの価格を決めるのだ、という創立者二人の信念と、それには自らがビジネス倫理にきびしい、honest company でなければならない、という企業倫理には絶対的な重みがあった。そういうビジネスをしている会社が一方では業者に値引きを要求すような行為は決して許されない、という考え方は Company Objectives という基本的ガイドラインして社員全体に徹底されていた。小生の提案をはねつけた男にすればガバナンス、などということではない、現場として当然の判断だったのだ。
それから何年か経ち、こんどは営業部門に代わった時の事、日本経済は円高の嵐にもまれていた時期である。YHP では日本の顧客むけに日本生産の製品を届ける一方、HPの各国工場から輸入したものを販売するという、いわば輸入商社としての活動も重要だった。定価販売、という原則でやっているから、円の価格は一定であり、したがって円高のおかげでその差額がいわば不労所得的に入ってくる。これは輸入販売の世界ではいわば当然のこととして容認されていた。ところが、当時のマネジメントは,これは honest company を社是とする会社の ” the way we do business at HP ” ではない、として、その ”不労所得” にあたる部分を顧客に返す、という行動に出た。もちろん、実現するにはいろいろな問題があるので、現実には主に大口顧客に対してだったが、この話をある著名な顧客に持っていく、という役目を仰せつかった。常識に外れた申し出に面食らった先方に理解していただくのがまず大変だった。しかし最終的には、先方が半分あきれながら、”HPさんの誠意はよくわかりました” といってくれ、当方もいい気分で落着した。この honest policy は理解され、その後為替レートの変動に合わせての値上げにも反発なく受け入れてもらえる結果になった。
このふたつの経験は何を意味しているか。現場が会社の経営理念を理解し、消化することが出来ていれば、結果として企業の運営は間違いなく機能するはずだ、という創立者二人以来の信念が全社にいきわたり、”the way at HP” が完全に機能していたからだろう。今問題になっているガバナンスという意味を管理が行き届かなかった、とか、手順書に記載がなかった、などととらえるのは本質を矮小化し、小手先のことに責めを負わせる言い訳にすぎない。今必要なのは、会社の基本理念に立ち返りその徹底をはかるだけの度量なのではないか、と思うのだが。