冬季オリンピックのこと (44 安田耕太郎)
歴代最多数メダル獲得、日本にとって上出来のアチーブメント。本
今年の冬季五輪を過去2つの五輪と比較します。参加国・地域数、
1. 猪谷千春が日本最初のメダルを獲った1956年コルチナダンペッ
参加国・地域数32
参加人数820人
競技種目数:
4競技24種目
因みにアルペンスキー3冠のトニー・ザイラーは2位との差、滑降
(長野オリンピックで魂のジャンプを見せた原田雅彦。最後のジャンプ中継でアナウンサの ”原田、立ち上がれ、立つんだ、立ってくれ、原田!” という絶叫が記憶に残る。
2. 1998年長野オリンピック:
冬季五輪開催地のうち最南で、最も低緯度地。
参加国・地域数72
参加人数
2,302人(男子1,488人、女子814人)
競技種目数
7競技68種目
金銀銅メダル総数204
3. 2026年ミラノ・コルチナダンペッツオ:
8競技116種目
参加国・地域数93
参加人数3500人
金銀銅総数:348
(長野五輪より7割、144個増加)。日本現在(2/18終了時
冬季五輪開催地について私見:
リレハンメル、スコーバレー、インスブルック、サッポロ、コルチ
26年2月 月いち高尾 (51 斎藤邦彦)
 今回の一般コースは冬晴れの生藤山から冠雪の富士山を展望するという計画でした。生藤山は「月いち高尾」では今までに4回計画して1度しか登頂できていない「鬼門」とされ、今回も創始者のジャイさんから「生藤山が消燈山にならないように!」と揶揄されながら企画したコースでした。
今回の一般コースは冬晴れの生藤山から冠雪の富士山を展望するという計画でした。生藤山は「月いち高尾」では今までに4回計画して1度しか登頂できていない「鬼門」とされ、今回も創始者のジャイさんから「生藤山が消燈山にならないように!」と揶揄されながら企画したコースでした。
前日も翌日も素晴らしい晴天で「なぜこの日だけがみぞれが降ったのか」不思議な天候のなか、早々に行先を高尾山に変更しての山行でした。結果的には普段より登山客が少ない高尾山の山頂で久しぶりに全員揃って記念写真に納まることができ、楽しい一日でした。
1.日時:令和8年(2026)2月17日(火)
2.コース別の山行記録(敬称略、()内は昭和卒年)
(1)シニアコース
<参加者 8名 記録者:村上裕治>
鮫島弘吉郎(36)大塚文雄(36)遠藤夫士男(36)岡沢晴彦(39)藍原瑞明(40)吉田俊六(44)村上裕治(46)平井利三郎(47)
今回は、「ロープウェイパーティー」「高尾梅園パーティー」「萩原作業道パーティー」の3つのパーティーに分散し、天狗集中とした。
<山行記録>
上り1h35m 下り1h7m 合計2h42m 登り 463m 下り 428m
高尾山口駅9:41 ⇒(1時間37分)⇒11:18高尾山(昼食)12:02⇒(1時間30分)⇒ 日影バス停 13:43
稲荷山コース 前日から降雪だったが路面の雪は、少なかった。頂上 前夜からの雪のためか登山者は少なかった。
萩原作業道 頂上西石階段及び5号路北半分が伐採工事のため通行できず。う回路(5号路南部分)を選択し、モミジ平北側道を歩く。大垂水峠分岐から、萩原作業道上部口に入る。ここからは、人に会うこともなく萩原作業道口下まで一気に下る。日影林道も雪はなく、日影バス停まで歩いた。
<工事予定>
山頂周囲一部通行止め 2/16-21 4号路通行止め 2/19-20
<ヤマレコ>記録ID:9300023 (高尾山 萩原作業道)でアップしました。
(2)一般コース(世話人:斎藤邦彦、齋藤伸介)
<参加者(9名)>
安田耕太郎(44) 福本高雄(47)水町敬(47)五十嵐隆(51)斎藤邦彦(51)桑原克己(52) 後藤眞(59) 齋藤伸介(63)大場陽子(BWV)
<山行記録>
上野原駅8:30⇒(JR+京王線)⇒高尾山口駅9:30⇒(45分)⇒10:15稲荷山10:30⇒(45分)⇒11:15高尾山頂12:00⇒(30分)⇒ケーブル山頂駅12:30⇒(1時間)⇒13:30高尾山口駅
午前8時過ぎに全員がJR上野原駅に集合。天気予報では午前中の早い時間に雨は上がると言っていたが氷雨はみぞれに代わり、しとしとと降り続き止みそうもない。乗車予定のバスの発車前に計画を変更し高尾山に行先を変更することとした。
高尾山口の駅前に着くとすでにそこにはシニアコースのメンバーが到着していて怪訝な表情で迎えられる。高尾山口駅前で「仕切り直して」登山を再開する。うっすら雪が積もりやや足元が悪いので稲荷山コースを選択した。みぞれは小雪に代わりちらほらと舞い続ける。コースタイム通り1時間30分で頂上に到着、シニアコースと合流し全員そろって昼食を取り、山頂標識前で記念写真を撮影する。
下りは「萩原新道コース」「1号路」「ケーブルコース」に分かれて天狗飯店を目指した。
(3)懇親会
<懇親会の模様>奥高尾の観梅コースを歩いた相川正汎さん(41)猪俣博康さん(43)も懇親会から参加し、にぎやかな懇親会となりました。奥高尾の梅の開花はまだしばらくかかりそうなので3月の会に期待が持たれます。
いつものように谷合さんのご好意で天狗飯店を貸切りにしていただき、ゆったりと懇親を楽しむことができました。今回初参加は桑原さんでしたが、初参加恒例の歌唱として「古びしわが山の小屋」を選び、併せて小屋の様子を報告してもらいました。日本海側は記録的な豪雪ですが浅貝だけはあまり降ってないとのことです。
(4)フォトアルバムは以下のURLからご覧ください。
https://photos.app.goo.gl/Hiip8R45y
4号路通行止め 2/19-20
<ヤマレコ>
記録ID:9300023 (高尾山 萩原作業道)でアップしました。
(2)一般コース(世話人:斎藤邦彦、齋藤伸介)
<参加者(9名)>
安田耕太郎(44) 福本高雄(47)水町敬(47)五十嵐隆(51)斎藤邦彦(51)桑原克己(52) 後藤眞(59) 齋藤伸介(63)大場陽子(BWV)
<山行記録>
上野原駅8:30⇒(JR+京王線)⇒高尾山口駅9:30⇒(45分)⇒10:15稲荷山10:30⇒(45分)⇒11:15高尾山頂12:00⇒(30分)⇒ケーブル山頂駅12:30⇒(1時間)⇒13:30高尾山口駅
午前8時過ぎに全員がJR上野原駅に集合。天気予報では午前中の早い時間に雨は上がると言っていたが氷雨はみぞれに代わり、しとしとと降り続き止みそうもない。
乗車予定のバスの発車前に計画を変更し高尾山に行先を変更することとした。
高尾山口の駅前に着くとすでにそこにはシニアコースのメンバーが到着していて怪訝な表情で迎えられる。
高尾山口駅前で「仕切り直して」登山を再開する。うっすら雪が積もりやや足元が悪いので稲荷山コースを選択した。みぞれは小雪に代わりちらほらと舞い続ける。
コースタイム通り1時間30分で頂上に到着、シニアコースと合流し全員そろって昼食を取り、山頂標識前で記念写真を撮影する。
下りは「萩原新道コース」「1号路」「ケーブルコース」に分かれて天狗飯店を目指した。
(3)懇親会
<懇親会の模様>
奥高尾の観梅コースを歩いた相川正汎さん(41)猪俣博康さん(43)も懇親会から参加し、にぎやかな懇親会となりました。奥高尾の梅の開花はまだしばらくかかりそうなので3月の会に期待が持たれます。
いつものように谷合さんのご好意で天狗飯店を貸切りにしていただき、ゆったりと懇親を楽しむことができました。今回初参加は桑原さんでしたが、初参加恒例の歌唱として「古びしわが山の小屋」を選び、併せて小屋の様子を報告してもらいました。
日本海側は記録的な豪雪ですが浅貝だけはあまり降ってないとのことです。
(4)フォトアルバムは以下のURLからご覧ください。
https://photos.app.goo.gl/Hiip8R45y8mD1U1C8
(期間限定でのアップですので必要な写真はダウンロードして下さい。)
(編集子)そうでないことを祈っていたが 生藤山すなわち消燈山、のジンクスはまたまた起きたようだ。次回、これを破るのはいつ?そういう小生も当日不調のため欠席してしまったので大きいことは言えないが。リポートによれば、また新しいメンバーの参加があった由、嬉しい限りだ。
(52 桑原)先日は、楽しい高尾山山行、有り難うございました。お陰様で、久しぶりに素敵な山行を楽しめました。また、沢山の写真ありがとうございます。記念・思い出になります。
匂いが分かったらキミも一安心 (普通部OB 篠原幸人)
病院で、診察かばんを持って歩いている医師を見かけたことはありませんか? 聴診器はポケットにも入るし、首からぶら下げても歩けます。但し、患者さんの脳や神経系(精神系ではありません)の異常をチェックするのに使用される打腱器(膝の下などを叩いて反射を見る道具)や眼底鏡、感覚低下を調べる筆やルーレットなどは可なりかさばるので、それらの道具をよく使う脳神経外科や脳神経内科の医師の多くは自分専用の道具を診察かばんに入れて持ち歩いていることが多いのです。
私も病院内では常時この鞄を持って歩いているのですが、私の場合ははその他に少量のコーヒー粉の入った小さなガラス瓶も入れています。
疲れた時に休憩でコーヒーを飲むためかって? 違います。診察の時に患者さんに目をつぶってもらい、鼻の穴の近くに蓋をあけたこの瓶を近づけて、何の匂いかを当ててもらうためです。だから時々新しいコーヒー粉に入れ替えることも必要です。古くなって匂いの消えた粉では検査にならないからね。
何故そんな事を調べるかって? 無論、鼻炎や花粉症、副鼻腔炎(俗に言う蓄膿症)の人は例外ですが、アルツハイマー病(認知症)やパーキンソン病では極く早期からこの匂いを嗅ぐ能力(嗅覚といいます)が落ちていることが多いのです。
皆さん、毎朝コーヒーの匂いを満喫して、少なくとも脳はまだ健康に生きているらしい喜びを満喫してください。また、今日から折に触れて、物の匂いをかいで回りましょう。
もっとも、台所であまりうろうろして物の匂いを嗅ぎまわっていると、邪魔者扱いされるか、手伝いに来たと誤解されるからご注意を!!
(編集子)ブランドにうるさい連中に馬鹿にされるけど、小生はドトールの店頭売りの粉を挽いてもらい我流で入れたものを飲んでる。カウンタで挽き方を聞かれるのが面倒( コーヒーメーカーの穴の数で香りが違いますから、って店員さんはもっともらしく言うけど、わかるわけはねえ、と思ってる―この辺、篠原ドクのご意見もあろうか?)なので、いつも8番!ともっともらしく言うことにしてる。8っていう数字が好きなだけで他に理由なんか、ない。ただ、まだ香りはするからドクのお世話にはかからなくて済みそうだ。
コーヒーメーカーの穴の数で香りが違いますから、って店員さんはもっともらしく言うけど、わかるわけはねえ、と思ってる―この辺、篠原ドクのご意見もあろうか?)なので、いつも8番!ともっともらしく言うことにしてる。8っていう数字が好きなだけで他に理由なんか、ない。ただ、まだ香りはするからドクのお世話にはかからなくて済みそうだ。
真っ白な北岳がうれしい朝です (グリンビラ総合管理HPより転載)
山行ノートから (1) (55 宮城裕之)
 昨年、台風来襲により急遽中止としたブナ立て尾根~読売新道~黒部湖をリベンジしました。天気は好天続きで、北アルプスの天水頼りの山小屋は、水不足となり、水の販売制限が1L/人、水のペットボトルは売り切れとなり、標高差1500mのブナ立て尾根は、水を5L担いで上がることになりました。裏銀座コースは好天が続くと予測されたため、昨年に比べて登山者多く、多くの登山者と話ができました。烏帽子岳~水晶岳までの稜線上からは、右側に、水晶岳~赤牛岳~読売新道のルートがよく見えて、また左側には、燕岳~槍ヶ岳までの表銀座の稜線がよく見えました。早朝はガスっていましたが、日の出とともに360度の大展望が続き、素晴らしい展望でした。3日目に水晶小屋から水晶岳・赤牛岳~読売新道を歩きましたが、前日良く見えた、歩きやすそうな稜線は、歩いてみると起伏が大きく思いのほか時間がかかりました。水晶岳~赤牛岳は大岩がゴロゴロして歩きづらく、読売新道は樹林帯に入る以前は、ザレ場・大岩ゴロゴロが続き、樹林
昨年、台風来襲により急遽中止としたブナ立て尾根~読売新道~黒部湖をリベンジしました。天気は好天続きで、北アルプスの天水頼りの山小屋は、水不足となり、水の販売制限が1L/人、水のペットボトルは売り切れとなり、標高差1500mのブナ立て尾根は、水を5L担いで上がることになりました。裏銀座コースは好天が続くと予測されたため、昨年に比べて登山者多く、多くの登山者と話ができました。烏帽子岳~水晶岳までの稜線上からは、右側に、水晶岳~赤牛岳~読売新道のルートがよく見えて、また左側には、燕岳~槍ヶ岳までの表銀座の稜線がよく見えました。早朝はガスっていましたが、日の出とともに360度の大展望が続き、素晴らしい展望でした。3日目に水晶小屋から水晶岳・赤牛岳~読売新道を歩きましたが、前日良く見えた、歩きやすそうな稜線は、歩いてみると起伏が大きく思いのほか時間がかかりました。水晶岳~赤牛岳は大岩がゴロゴロして歩きづらく、読売新道は樹林帯に入る以前は、ザレ場・大岩ゴロゴロが続き、樹林 帯に入ると太陽に照らされなくなり涼しくなりましたが、小さな岩や大木の根が湿気によりコケが生えて滑りやすく、何度か転倒して足を痛めました。読売新道は上りが少なく、ひたすら下る一方なので、コースタイム5時間のため、休憩時間を入れて4時間は切れるかと思っていましたが、意外に時間を要して、休憩時間を入れて5時間でした(実働は3時間30分)。奥黒部ヒュッテ~平の渡しまでは、早朝通過のためヘッドランプを付けての行動となりました。はしご・ザレ場の連続で、雪崩により壊れている箇所が3か所あり、下を流れる水の轟音が響きスリル満点でした。6月に68歳単独行の男性が落下し、亡くなったとのことで、緊張しながらの通過となりました。朝一番の渡し舟がAM6時出発であるため、3時起床、3時40分に奥黒部ヒュッテテントサイトを出発し、何とか1時間50分で平らの渡しに5:30到着。(船は6時15分発)黒部湖を横断する船は関西電力が無償で運航しているようで感謝です。平の渡し~ロッジクロヨンは、意外にも登り下りが多く、またハシゴ・ザレ場の連続で、こちらも3か所ほどは雪崩により崩れていました。黒部ダムまで来ると観光客が多く、ダムの上からは、はるか遠くに赤牛岳山頂が見えて感激でした。
帯に入ると太陽に照らされなくなり涼しくなりましたが、小さな岩や大木の根が湿気によりコケが生えて滑りやすく、何度か転倒して足を痛めました。読売新道は上りが少なく、ひたすら下る一方なので、コースタイム5時間のため、休憩時間を入れて4時間は切れるかと思っていましたが、意外に時間を要して、休憩時間を入れて5時間でした(実働は3時間30分)。奥黒部ヒュッテ~平の渡しまでは、早朝通過のためヘッドランプを付けての行動となりました。はしご・ザレ場の連続で、雪崩により壊れている箇所が3か所あり、下を流れる水の轟音が響きスリル満点でした。6月に68歳単独行の男性が落下し、亡くなったとのことで、緊張しながらの通過となりました。朝一番の渡し舟がAM6時出発であるため、3時起床、3時40分に奥黒部ヒュッテテントサイトを出発し、何とか1時間50分で平らの渡しに5:30到着。(船は6時15分発)黒部湖を横断する船は関西電力が無償で運航しているようで感謝です。平の渡し~ロッジクロヨンは、意外にも登り下りが多く、またハシゴ・ザレ場の連続で、こちらも3か所ほどは雪崩により崩れていました。黒部ダムまで来ると観光客が多く、ダムの上からは、はるか遠くに赤牛岳山頂が見えて感激でした。
(行動概要);七倉山荘~ブナ立て尾根~烏帽子小屋~水晶岳~赤牛岳~読売新道~黒部湖
7月30日(水); 自宅~(長谷川ピックアップ)→(上信越道)→麻績IC→信濃大町駅前ルートインホテル(泊) 車移動(280km;4時間)
7月31日(木); 宿泊先→信濃大町駅前~(裏銀座バス)~七倉山荘~(タクシー)~高瀬ダム⇒ブナ立て尾根登山口⇒烏帽子小屋⇒烏帽子岳⇒烏帽子小屋テントサイト(泊);
歩行距離(13km);コースタイム7時間10分(休憩時間2時間含む) 上り(1957m)・下り(492m)
8月1日(金):⇒烏帽子小屋テントサイト⇒三ツ岳⇒野口五郎岳⇒真砂岳⇒東沢乗越⇒水晶小屋(泊)
歩行距離(8.7km);コースタイム6時間31分(休憩時間1時間44分含む) 上り(837m)/下り(454m)
8月2日(土): 水晶小屋⇒水晶岳⇒温泉沢の頭⇒赤牛岳⇒奥黒部ヒュッテテントサイト(泊)
歩行距離(11.2km);コースタイム10時間45分(休憩時間3時間51分含む) 上り(436m)/下り(1836m)
8月3日(日) 奥黒部ヒュッテ⇒平ノ渡し場⇒ロッジクロヨン⇒黒部ダム→扇沢→信濃大町駅~
(車ピックアップ)~(大町温泉薬師の湯)→自宅;車移動(300km; 6時間30分)
歩行距離(15.1km);コースタイム7時間39分(休憩時間2時間16分含む) 登り1242m/下り1281m
(編集子)先に台湾遠征の記録を紹介したが、現役並みのアクティビティをキープしているグループの記録を紹介させてもらうことにした。その第一号である。聞くところでは5月にはまた、旧友を糾合してアルプス再踏破を計画しているとのこと。Boys, go for broke !
ミラノ・コルチナの快挙を聞きながら横丁老人の与太
衆院選と並行する形で耳目を集めているミラノオリンピック。イタリアと言えば西欧文化の中核であって、我々日本人にも現地を訪れたかどうかは別に、なじみのある国だし、街へ出ればピッザにスパゲティにとイタリア発祥のメニューが今や日本人の食文化の一部になっているほど、親しい感じのする国である。
そこで行われているオリンピック、なによりそのコルチナダンペッツオ、という地名に親しみがあるのは、かの猪谷千春選手の日本人初の銀メダル、というのが僕らの年代の反応だからだ。学生時代、35年卒の森永さんは当時松屋百貨店に勤務しておられた慶応OBのスキーの名手丸林先輩と知己の中で、松屋の応援があったのだろうが仲間内で丸林さんを囲むスキーバス、という夢みたいな企画をたててくれ、小生もそのお相伴にあずかって志賀丸池で二泊させてもらったことが ある。このプランに、実に猪谷千春さんとなんと杉山進さん、当時の日本を代表する、へっぽこスキーヤには雲の上の人たちが参加され一緒に滑ってもらったことがあった。猪谷さんは温厚なジェントルマン、という表現がぴったりする方だった。当時まだ、(ウエ―デルンはどうすりゃできるのか)なんて言っていたくらいの小生をご覧になって、紳士らしく一つくらいは言ってやろう、と思われたのだろう、猪谷さんから、(うん、あなたのボーゲンはなかなかいいよ)と言ってもらったものだ。このプランで、使っていたザックに猪谷さん、杉山さんのサインをもらって後生大事にしていたのだが、理由は覚えていないが後輩に持っていかれてしまった。37年の八野だったか、もしかすると39年の堀川だったか相川だと思うんだが覚えていない。該当者がいれば教えてくれ(返せたあ言わないから)。
ある。このプランに、実に猪谷千春さんとなんと杉山進さん、当時の日本を代表する、へっぽこスキーヤには雲の上の人たちが参加され一緒に滑ってもらったことがあった。猪谷さんは温厚なジェントルマン、という表現がぴったりする方だった。当時まだ、(ウエ―デルンはどうすりゃできるのか)なんて言っていたくらいの小生をご覧になって、紳士らしく一つくらいは言ってやろう、と思われたのだろう、猪谷さんから、(うん、あなたのボーゲンはなかなかいいよ)と言ってもらったものだ。このプランで、使っていたザックに猪谷さん、杉山さんのサインをもらって後生大事にしていたのだが、理由は覚えていないが後輩に持っていかれてしまった。37年の八野だったか、もしかすると39年の堀川だったか相川だと思うんだが覚えていない。該当者がいれば教えてくれ(返せたあ言わないから)。
さて先日の朗報、女子ビッグエアでの快挙に関係がある与太話だ。スキーを長年やっても、丸池のAコースだの八方尾根は名木山の急斜面なんかでふうふう言っていた程度の小生に、スキーではないにせよ同じ雪の上でこのような神業を論じる資格があるわけはない。ただただ、彼女たちの神業に呆然としながら、拍手、感激しながらつまらんことに気を奪われた。何か。入賞した選手たちの名前のことだ。
村瀬心椛、金メダルおめでとう! という気もちはもちろんあるんだが、新聞記事で名前を見た時、その名前を読むのに苦労した。椛をかんばの木、と読むのは調べて分かったが、この名前を ”ここも” と読むのは思いつかない。それとチームメートが 鈴木萌萌、でこれをもも、と読むのも難しい。さらに深田茉莉、これは確かにどっかで見た名前だけど、次の岩淵麗楽はれいら。年齢から推察するに彼女たちの名前をお考えになったご両親は小生の子供と同年齢なのだろうと推察する。そりゃあんたの子供ならそうだろ、だから何さ、一緒にしないでよ、という反論は想定のうえでいわせてもらえば、最近の若い人たちの名前には、どういったらいいのか、(!)と考えてしまうことが多々ある。
編集子大田区立赤松小学校6年生の昔、ほのかな思いを寄せていたのは5年生3組のひろこちゃん(正式には浅野姓で、今を時めく同姓同名綴りもおなじ花形女優が登場した時には―あったりまえだろ、かんけえねえがー、なんだかキュンとしたもんだ)、だったし、親戚友人並べてみても女性陣はまずなんとか子ちゃん・さんがほとんどなので、この種のキラキラネームにはなじめない。しいて言えば、会社時代、名コンビといわれた秘書がやよいさんだった、くらいだ。かたや、昭和末期から平成の、なんといっていいか、昭和元禄2.0ともいうべき一種の平穏の中で青春を送った姪たちに言わせると、“子” が付くと何やらやんごとなき血筋を思わせることがあって、いかにも古めかしい、という風潮があるんだそうだ。それに、私っ達、苗字がなんたって 司 だもんね、と自分もそのやんごとなき血筋と思われたかとほのめかすのだが、本人がやんごとなき血筋には程遠い、かの竹下通りなどを徘徊していた実情を知る叔父には信じがたい。同じナカツカサでも、中務姓はたしかに貴族系らしいが、中司姓は平家一門の雑兵だそうで、多くが壇ノ浦の海に沈んだ。その生き残りの人たちが住み着いたのが今でいえば広島、山口あたりなんだと祖母から聞いたことがある(彼女も山口県出身)。今度の維新幹事長がどうなのか、聞いてみたい気もするが、ま、とにかく、名前って、もっとわかりやすくって書きやすい(ご本人が一生書き続けるもんだからね)方がいいんじゃねえの、とは思うし、PCの漢字変換もめんどくさいんだが。
ここまで書いて気が付いた。俺は何を言いたかったんだろ。はたまた、昭和は遠くなりにけり、と結ぶんかなあ。これから登場するあのアユム君、当たりの名前は読みやすいしご両親が彼に期待したことも想像できる。ま、カンケ‐ねえけど、しっかり飛んでくれよな。
(普通部OB 田村耕一郎)1956年、猪谷千春選手のコルチナでの入賞は日本を明るくしてくれた大快挙と、興奮し感激しました。そしてダートマス大学という名門大学の名を知りました。70年たち、若い人のスノーボードでは日本大国との活躍は凄いですね。連日嬉しいニュースが続き、政治選挙ニュースを吹き飛ばし感謝です。
猪谷さんが2位だった伝説のレース、1位はかのトニー・ザイラーだった。写真は飯田武昭君のご提供による。このレースを伝えたある記事は、(この日本人は猫のように滑り降りていった)と書いていたそうだ。また、黒い稲妻 を見たくなった。
(HPOB 小田篤子)以前メールに載せたことがあるかと思いますが、
エーガ愛好会 (358) ダウントン・アビー・グランドフィナーレ (34 小泉幾多郎)
TV放映のエーガは観ているが、映画館での鑑賞は何年振りか。「ダウントン・アビー」TV版は、シーズン1の1912年から、1925年のシーズン6シリーズ52作が制作され、その間、映画が2作制作されている。その第1作(2020.1.19)は映画館で観ている。その後TV放映エーガは観ているが、映画館での鑑賞は、何年振りか記憶にない。この映画第1作については、2020年2月12日に新春映画三昧と称し、ブログに掲載されたが、「ダウントン・アビー」は貴族とその使用人との15年史を変わりゆく価値観と人生の集大成として、貴族文化の終わりと現代へ続く最終章が描かれた。TVでは、1912年から1925年に至る、シーズン6シリーズ、52話が制作された。この映画第1作は1927年ダウントン・アビーに国王夫妻が滞在する一報が、冒頭、蒸気機関車で通知されるが、TV版第1作の冒頭で、ダウンタウンの相続人がタイタニック沈没で死亡したことを通知することから始まる壮大な物語の始まりと対を成すものだった。
映画第2作新たなる時代へは、2022年にパリ在住の平井さんから紹介があり、1928年以降の屋敷の維持費用の工面に頭を悩ませる物語リが描かれたとのことだが、TV放映を期待して観ない儘、その後TV放映なき儘に(Wowowでは放映したらしい)見逃してしまった。
映画第3作は1930年代となり、屋敷が次世代へ託される時代に、娘メアリーは、離婚に晒されながら、貴族と使用人たちの新しい門出へ決着を付けられて行く。貴族文化に終わりを告げながらも終結を迎えるのだった。ダウントンの屋敷が次世代へと託されることになるが、父ロバーツから娘メアリーが経営者としての自立を、また使用人たちにも新たな門出が訪れる。ドラマティックな愛憎劇もあったが、ロケーションンの美しさ、衣裳の美しさ等ロケーションの美しさも楽しませてくれた。TVシリーズ完結から4年後2019年劇映画第1作、2022年第2作、2025年第3作と楽しませてくれた。
建国記念日‐紀元節のことです (普通部OB 船津於菟彦)
大日本帝国時代には、紀元節や紀元2600年式典などの国家行事
紀元2600年には、東京オリンピックや万博など、数々の奉祝行
不思議とこんな難しい歌詞の一部が口ずさめますね
金鵄(きんし)輝く 日本の
栄(はえ)ある光 身にうけて
いまこそ祝へ この朝(あした)
紀元は二千六百年
ああ一億の 胸はなる
歓喜あふるる この土を
しつかと我等 ふみしめて
はるかに仰ぐ 大御言(おおみこと)
紀元は二千六百年
ああ肇国(ちょうこく)の 雲青し
荒(すさ)ぶ世界に 唯一つ
ゆるがぬ御代(みよ)に 生立ちし
感謝は清き 火と燃えて
紀元は二千六百年
ああ報国の 血は勇む
潮ゆたけき 海原に
桜と富士の 影織りて
世紀の文化 また新た
紀元は二千六百年
昨日は天気が良くて、気持ちよかったので亀戸天神梅まつりに行ってきました。
(編集子)神武天皇にさかのぼるこの国が建国2600年になる、とされたのが昭和15年,編集子はまだ3歳、だからわかるわけはないが、兄や母が口ずさんでいた、この ”きげーん にせんろっぴゃーくねーん” という一節は幼いころから知っていた。憲法が世界の実情に対応するべく改められたとき、どんな歌がうたわれるのだろうか。
しかし建国記念日の当日、それを語る報道番組は見当たらなかった。読売新聞ですら、1行の記事も見当たらなかった。なんとなくおさまらない感じがした。
乱読報告ファイル (60) なんとモーパッサンを読んだのだ (普通部OB 菅原勲)
 フランスはギイ・ド・モーパッサンの中短編10編ほどを編纂した「脂肪の塊」/「ロンドリ姉妹」モーパッサン傑作選中の中編「脂肪の塊」(1880年、翻訳:太田浩一、発行:光文社古典新訳文庫/2016年)を読んだ。
フランスはギイ・ド・モーパッサンの中短編10編ほどを編纂した「脂肪の塊」/「ロンドリ姉妹」モーパッサン傑作選中の中編「脂肪の塊」(1880年、翻訳:太田浩一、発行:光文社古典新訳文庫/2016年)を読んだ。
「脂粉の塊」と言う題名から真っ先に受ける印象は、真面なものではなく、正にドロドロしたものだ。その内容もその通りで、「脂粉の塊」と綽名された娼婦が主人公となっている。
普仏戦争(プロシャ、ドイツ)により、フランスのルーアンがプロシャに占領され、その内の10人ほどが、プロシャの総司令官の許可を取り付け、フランス軍の支配下にあるル・アーヴレに辿り着くことを画策する。乗客は、ワイン問屋を営んでいるロワゾー夫妻、伯爵夫妻、上流階級の夫妻、二人の修道女、それに、民主主義者、「脂粉の塊」と綽名された娼婦。
この旅の途上、小生にとって誠に許し難い事態が発生する。トートと言う町の旅籠で一泊するのだが、翌朝の出発の準備が全く整っていない。どうやら、「脂粉の塊」が当地はプロシャの士官の要求を拒んだことが、留め置かれている原因らしいと判明する。そこで、人間の持つ醜いエゴイズムが赤裸々となる。その一つは、伯爵が、彼女を外に連れ出してこう説得する。「・・・それでも、あの士官の望みをかなえてやるのは嫌だというわけかな。そうした要求には、いままで何度も応えてきたのではありませんか」。もう一つは、ホテルに残った連中が、二人の修道女から、「・・・たとえ、よからぬ行為であったにせよ、その動機いかんによっては、しばしば賞賛されることもございますから」との言質を取り付ける。一晩明けると、無事、乗合馬車は出発する。ところが、途中での食事に対する感謝もなければ、この一夜に対する労いもなく、最後まで汚物でもあるかのように扱われ、「脂粉の塊」は、全員からほっておかれる。途中のディエップに到着と同時に、泣き崩れる「脂粉の塊」で、話しは終わる。何とも酷い、途轍もなく酷い話しだ!こんな愚にもつかぬ話をフォードが映画でやる筈はない!器は、確かに、いずれも駅馬車と乗客だろうが、その中味は正に水と油であり、全くの別物だ。つまり、モーパッサンの「脂粉の塊」とフォードの「駅馬車」は何等の関係もない。
しかし、小生、一体、何故、こんな本を態々読んだのだろう。それは、映画「駅馬車」(1939年)を監督したジョン・フォードが、「駅馬車」は、実は、このモーパッサンの「脂肪の塊」だと語っていることを知ったからだ。そこで、今更なのだが、野次馬根性で、このモーパッサンを読んで見た。確かに、駅馬車(この本では、乗合馬車と言っている)とそれに乗っている人たちの人間模様を描いている点では、それこそ、エーガ「駅馬車」と言えるだろう。しかし、これは換骨奪胎であって、フォードの「駅馬車」の白眉である駅馬車とインディアンとの壮烈、熾烈な追っかけっこは全くないし、当然のことながら、モーパッサンにはインディアンのイの字も全く出て来ない。しかも人間模様を描くと言っても、フォードには、いつもの通り人の温みはあるものの、間違ってもモーパッサンの様にドロドロしたものはいささかも存在していない。
有体に言ってしまえば、フォードの「駅馬車」は「脂粉の塊」の駅馬車と乗客を刺身のつまとして拝借しているだけで、逆に、「駅馬車」は、「脂粉の塊」とは全く無縁のインディアンの攻撃なくして成り立たなかった。そう考えると、何故、フォードが「駅馬車」はモーパッサンの「脂粉の塊」だと言ったのか、その真意が、ボンクラの小生には皆目分からない。
最後に、職業に貴賤なしと言うが、この本は、娼婦にたいする誠に汚らわしくも卑劣極まりない途轍もないイジメがある。最後は娼婦の涙と共に終わるのだが、繰り返すが、これは途轍もなく酷い。
「ボヴァリー夫人」の作家であるフローベールも、傑作だと言って絶賛しているが、小生に言わせると、愚作、駄作以外の何物でもない。あっ、そう言えば、「ボヴァリー夫人」も愚作、駄作だった。
*******************************************************************************
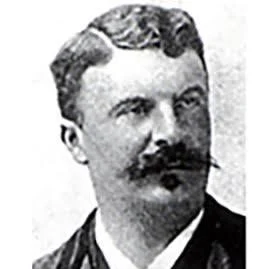 アンリ・ルネ・アルベール・ギ・ド・モーパッサン、通称ギ・ド・モーパッサンは、フランスの自然主義の小説家、劇作家、詩人。『女の一生』などの長編6篇、『脂肪の塊』などの短篇約260篇を遺した。 エミール・ゾラの主宰した短編集『メダンの夕』に入れた『脂肪の塊』の評判が高く、作家としての地位を確実にした
アンリ・ルネ・アルベール・ギ・ド・モーパッサン、通称ギ・ド・モーパッサンは、フランスの自然主義の小説家、劇作家、詩人。『女の一生』などの長編6篇、『脂肪の塊』などの短篇約260篇を遺した。 エミール・ゾラの主宰した短編集『メダンの夕』に入れた『脂肪の塊』の評判が高く、作家としての地位を確実にした









