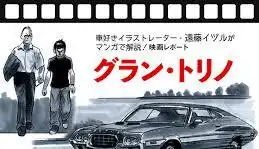本日は敬老の日。
敬老の日は、国民の祝日として1966年(昭和41年)に設けられ、「長年社会に貢献してきた老人を敬愛し、長寿を祝い、老人福祉への関心を深める」ことを趣旨としています。2002(平成14年)年までは毎年9月15日でしたが、2003年(平成15年)から、9月の第3月曜日となり、敬老の日は年ごとに変わります。今後この制定に変更がなければ、2026年は9月21日(月)、2027年は9月20日(月)となります。
敬老の日の由来は、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)村長であった門脇政夫氏が、「老人を大切に、お年寄りの知恵を借りて村作りをしよう」という趣旨で、1947年(昭和22年)9月15日に「敬老会」を開催したことが始まりとされています。翌年の9月15日には「としよりの日」として村独自の祝日となり、1950年(昭和25年)に兵庫県が「としよりの日」を制定。1951年(昭和26年)には、中央社会福祉協議会(現全国社会福祉協議会)が「としよりの日」を定め、1966年(昭和41年)に現在の「敬老の日」となりました。
総務省は14日、15日の「敬老の日」に合わせ、65歳以上の高齢者の推計人口(15日現在)を発表しました。高齢者は3619万人と前年から5万人減少したが、総人口に占める割合は0・1ポイント上昇して29・4%と過去最高を更新した。昨年の高齢者の就業者数も930万人と21年連続で増加し、過去最多。 高齢者の減少は2年ぶりで、増加数よりも死者数の方が多かったことなどが要因だそうです。高齢者の割合は1950年から増え続けていて、国立社会保障・人口問題研究所は、2050年には37・1%に達すると推計しています。
以前は、還暦を迎えた60歳からお祝いをする風潮がありましたが、現在の60歳はまだ現役というイメージも強く、「年寄り扱いされたくない」と考える方も少なくありません。気持ちも若々しい現代のシニア世代は、何歳になってもおじいちゃん扱い、おばあちゃん扱いされたくないという考えの方もいらっしゃいます。その場合は、退職や、孫が生まれた年、古希(70歳)、傘寿(80歳)など節目を迎えた年がお祝いしやすいタイミングです。
「年寄り」とは法律では、老人福祉法が「(老人ホームへの入所などの対象が)65歳以上の者」としているほか、国民年金法でも「老齢基礎年金の支給は65歳に達したとき」などとなっており、放送でも以前は65歳を「老人」という語を用いる場合の一つの目安にしていたようです。
しかし、高齢化社会が進み平均寿命もグーンとのびた今の時代に、この年齢以上の人たちを一概に「老人」「お年寄り」とするには無理があるようです。今や人生100歳時代を謳歌している方がゾロゾロ。しかし、少子化で高齢者のみの社会になりかねない。
国際連合は、2050年には世界人口の18%が65歳以上となると予測、OECD諸国においては現加盟国の全てにおいて、2050年には1人の老人(65歳以上)を3人以下の生産人口(20-65歳)にて支える超高齢社会となると予測されています。
高齢者人口が減少に転じても高齢化率は上昇を止めず、2065年には高齢化率が38.4%、その中でも75歳以上は25.5%にまで達し、国民の約2.6人に1人が65歳以上、3.9人に1人は75歳以上であると推計されています。
日本政府の高齢社会対策大綱の方針は 「高齢社会に暮らす全ての世代の人々が安心して幸せに暮らせるよう、人々が若年期から計画的に高齢期に向けた備えを進めるとともに、各世代が特有の強みをいかしながら多世代のつながりを醸成し、全ての世代の人々が高齢社会での役割を担いながら、積極的に参画する社会を構築するための施策を推進する。」 だそうです。なんだかなあ。