宝塚歌劇に多少の興味をお持ちの方へ、“知っていて損ではない ”程度の話ですが・・・・
演目「GUYS and DOLLS」の公演予定は宝塚大劇場 7月26日~9月7日、東京宝塚劇場 10月4日~11月16日)ですが、宝塚歌劇で度々公演プログラムに乗るこの演目は、元々はニューヨークのブロードウエイのヒット・ミュージカルがオリ ジナルで、映画化は1955年に監督ジェセフ・L・マンキウイッツ主演:マーロン・ブランド、フランク・シナトラ、ジーン・シモンズの邦題「野郎どもと女たち(GUYS and DOLLS)」で、日本でも当時、劇場公開された時に楽しみに観に行きました。
ジナルで、映画化は1955年に監督ジェセフ・L・マンキウイッツ主演:マーロン・ブランド、フランク・シナトラ、ジーン・シモンズの邦題「野郎どもと女たち(GUYS and DOLLS)」で、日本でも当時、劇場公開された時に楽しみに観に行きました。
ところが、この映画には良い曲、良いダンス・ナンバーは幾つかあるものの、ミュージカル映画としては興行的に失敗作で、その主な原因は主役のマーロン・ブランドのミス・キャストだと新聞各紙共が伝えていたと記憶しています。
 マーロン・ブランドは当時、「欲望という名の電車」(1951年)で、衝撃的なデビューをし、続く「革命児サパタ」「ジュリアス・シーザー」「乱暴者」そして、名作「波止場」(1954年)と飛ぶ鳥を落とす勢いの俳優でしたが、この「野郎どもと女たち」(1955年)頃から、何故かヒット作が減り「ゴッド・ファーザー」(1972年)までは不遇に喘いでいたように思えます。
マーロン・ブランドは当時、「欲望という名の電車」(1951年)で、衝撃的なデビューをし、続く「革命児サパタ」「ジュリアス・シーザー」「乱暴者」そして、名作「波止場」(1954年)と飛ぶ鳥を落とす勢いの俳優でしたが、この「野郎どもと女たち」(1955年)頃から、何故かヒット作が減り「ゴッド・ファーザー」(1972年)までは不遇に喘いでいたように思えます。
主役のこれほどのミス・キャストは他には直ぐには  思い出せないような、奇妙な面白さがある映画です。
思い出せないような、奇妙な面白さがある映画です。
(42 保屋野)確かに、マーロン・ブランドとミュージカル・・ちょっと想像できませんね。宝塚は大昔,浜木綿子や加茂さくら、淀かほる等が活躍していたころ、テレビでよく観ていましたが、姉から「男のくせに」と、からかわれた記憶もあります。宝塚も一度劇場で観たいとは思いますが「見果てぬ夢」となりそうです。
なお、私は、自慢ではありませんが(笑)学校の授業で能を一度観ただけで、歌舞伎、狂言、文楽は(食わず嫌いで)観たことがありません。寄席も一度ぐらいしか記憶にないし、伝統芸能が嫌いというわけではないのですが、興味がわかない、というか・・。日本人失格ですね。ちなみに、一度観てみたいのが、京都の「都踊り」そして「阿波踊り」と「風の盆」・・歌手では「新妻聖子」のコンサート。
(44 安田)確か、愛好会の皆さんに送付した記憶がありますが、菅原さんの映画「エデンの東」鑑賞後のジェームス・ディーン評に僕が返答のコメントを記す形でメモを作成しています。更に同時期放映された「エデンの東」についての愛好会メンバー数名の投稿文を集めwordfileにまとめました。2020年10月のことです。宜しければこちらも併せてお読みください。5年の歳月が経っていますが。愛好会の皆さん(安田を含め)熱き頃の投稿文集です。
 (編集子)”風と共に去りぬ” でヴィヴィアン・リーが演じたスカーレットが当初の予定はスーザン・ヘイワードだった、というような話を聞いたことがある。エーガに限らず、人生ミスキャストがもたらしたものは数多い
(編集子)”風と共に去りぬ” でヴィヴィアン・リーが演じたスカーレットが当初の予定はスーザン・ヘイワードだった、というような話を聞いたことがある。エーガに限らず、人生ミスキャストがもたらしたものは数多い だろう。多くの場合、結果がよくないことを暗示するようだが、参院選の結果のキャスティングがどう収まるのか、興味津々、というところだ。
だろう。多くの場合、結果がよくないことを暗示するようだが、参院選の結果のキャスティングがどう収まるのか、興味津々、というところだ。
グーグルサーチしてみたら、スーザンとクラーク・ゲーブルのツーショットがみつかった。もし、”風”の主役がこの二人だったら、どんな仕上がりだった のだろうか。小生もヘイワードにはたびたびお目にかかっているが、まだ無名だったころ、ゲイリー・クーパー,レイ・ミランド、ブライアン・ドンレヴィという当時のスターに囲まれていた、 ”ボージエスト” での初々しい印象が強い。あの役がヴィヴィアンだったらどうだっただろうか。キャスティング、というのはなにかと想像を掻き立てるものだ。
のだろうか。小生もヘイワードにはたびたびお目にかかっているが、まだ無名だったころ、ゲイリー・クーパー,レイ・ミランド、ブライアン・ドンレヴィという当時のスターに囲まれていた、 ”ボージエスト” での初々しい印象が強い。あの役がヴィヴィアンだったらどうだっただろうか。キャスティング、というのはなにかと想像を掻き立てるものだ。
 (
(
(34 小泉) 宝塚歌劇には家内がファンなもので、多少の興味はあります。家内は宝塚歌劇ツアークラブに入り、チケット購入を試みてますが、相変わらず人気が高く、思うようにはチケットの購入は出来ないようです。偶々今回ご紹介の「GUYS and DOLLS」は10月のチケット購入出来たということで楽しみにしているようです。昨年購入の「宝塚歌劇110年史」を見せて貰ったら、「宝塚歌劇と海外ミュージカル」という欄があり、宝塚における海外ミュージカル第1作は1967年の「オクラホマ」で、第2作が1968年の「ウエストサイド物語」。この第2作は、演出家ジェローム・ロビンスの直弟子サミー・ベイスによる猛稽古を重ね11月の東京公演で芸術大賞を受賞しています。その舞台を珍しくも家内と一緒に見て、映画の場面と寸分違わぬような出来に感心した記憶が残っています。
その後、「回転木馬」「南太平洋」「ショーボート」「フラワードラムソング」「「ロミオとジュリエット」「雨に唄えば」「MEAND MY GIRL」等々海外ミュージカルの上演は続いているようです。 映画「野郎どもと女たち」も観ましたが、野郎=マーロン・ブランドで、当時は何の違和感もありませんでした。
 映画は190
映画は190 (編集子)小生にとって、マクラグレンとはどこまでいってもフォード騎兵隊ものの常連だった父親のほうであり、ヘストンは 大いなる西部 の頑固者であり、コバーンは出世作、荒野の七人 の口数少ない凄腕のナイフ使いの役とその最後のナイフが突き刺さるカットが忘れられない。その後いろいろな作品を見たが、これに勝る記憶はない。そのせいか、この作品にはあまり熱がはいらなかった。ドクコイズミ、申し訳ない。
(編集子)小生にとって、マクラグレンとはどこまでいってもフォード騎兵隊ものの常連だった父親のほうであり、ヘストンは 大いなる西部 の頑固者であり、コバーンは出世作、荒野の七人 の口数少ない凄腕のナイフ使いの役とその最後のナイフが突き刺さるカットが忘れられない。その後いろいろな作品を見たが、これに勝る記憶はない。そのせいか、この作品にはあまり熱がはいらなかった。ドクコイズミ、申し訳ない。
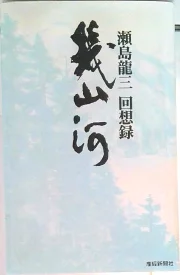

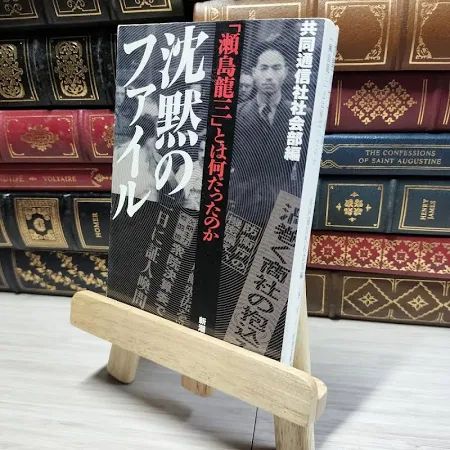








 (
(