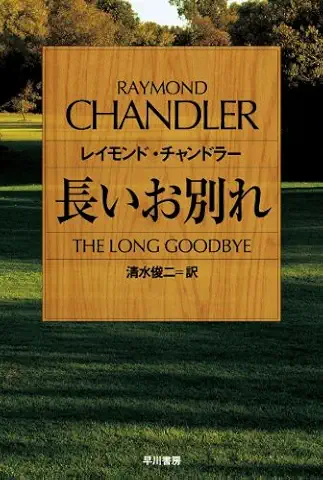令和7年最後の「月いち高尾」は忘年山行と銘打って冠雪の富士山を高尾山と高川山の両方から眺望する企画としました。絶好のコンデションのもと大いに楽しめた一日でした。
令和7年最後の「月いち高尾」は忘年山行と銘打って冠雪の富士山を高尾山と高川山の両方から眺望する企画としました。絶好のコンデションのもと大いに楽しめた一日でした。
1.日時:令和7年(2025)12月23日(火)
2.コース別の山行記録(敬称略、()内は昭和卒年)
(1)シニアコース <参加者(16名)世話人:村上祐治>
鮫島弘吉郎(36) 中司恭(36)大塚文雄(36) 高橋良子(36) 浅海昭(36) 鮫島弘吉郎(36) 遠藤夫士夫(36) 三嶋睦夫(39) 岡沢晴彦(39) 立川千枝子(39) 藍原瑞明(40) 武鑓宰(40)相川正汎(41) 保屋野伸(42) 下村祥介(42) 猪俣博康(43) 村上裕治(46)中里幸雄(51)
<山行記録>
〇ロープウェイ組:高橋良子、鮫島弘吉郎、浅海昭、遠藤夫士男、大塚文雄、岡沢晴彦、三嶋睦夫、立川千枝子、藍原瑞明、武鑓宰、相川正汎、猪俣康博
〇稲荷山組:下村祥介、保屋野伸、中里幸雄、村上裕治
往路は、トップの保屋野さんが飛ばして、1時間30分を切り、皆さん満足でした。 復路は、郵便道(逆沢作業道)経由、日影バス停まで、50分で下り、誰にも出会わず、静かな奥高尾でした。 その後、旧甲州街道を少し歩いて、珈琲自家焙煎店「ふじだな」まで行きました。火曜は、お休みで残念!
(2)一般コース(世話人:斎藤邦彦)<参加者(11名)>
安田耕太郎(44)徳尾和彦(45) 家徳洋一(50)保田実(51)五十嵐隆(51)斎藤邦彦(51)後藤眞(59) 鈴木一史(60)木谷潤(62) 齋藤伸介(63)大場陽子(BWV)
<山行記録>
アプローチ 高尾駅7:40⇒(中央線50分)⇒8:30初狩駅
集合:JR初狩駅前8:30
コースタイム(登り418m1時間40分)(下り583m1時間30分)
初狩駅458m8:30⇒(30分)⇒高川山登山口559m9:00⇒(20分)⇒9:20男坂女坂分岐 730m9:50⇒(50分)⇒10:40高川山976m11:10⇒(1時間30分)⇒12:40山梨リニア実験センター13:15⇒(バス15分)⇒13:30大月駅 13:48⇒(JR中央線37分)⇒14:25高尾駅
駅から直接登れ、均整の取れた富士山の眺めを始め360度のパノラマが楽しめる人気の山としての高川山に登るコースです。全員が時間通りの電車で8時30分に中央線の初狩駅に集合。気温零度近い寒さの中、準備体操の後出発しました。
快調に住宅地を抜け登山口から参道に入る。木の根が張り出した道や九十九折りの道を辿り男坂/女坂の分岐まで進む。ここで一本を取り服装の調整と数人からのお菓子の振舞いを受ける。休憩後は迷わず男坂に取り付きところどころにロープ場がある急登をぐいぐいと高度を稼ぐ。8合目あたりから樹間に頂上に雪をかぶった富士山が見え始め元気づけてくれる。そのまま頂上までほぼコースタイム通りの歩みで到着、180度のパノラマが開ける。早速富士山をバックに記念写真をとり、楽しい昼食時間となった。
下りは古宿ルートを一気に下りリニアモーターカーの見学センターに出て富士急行の路線バスで大月駅まで帰途に着いた。
(3)懇親会
<懇親会の模様>
いつものように谷合さんのご厚意で天狗飯店を貸切りにしていただき、ゆったりと懇親を楽しむことができました。また今回は24人と参加者が多く大御所の36年卒業組が7人の参加で大変にぎやかな会でした。
(4)フォトアルバムは以下のURLからご覧ください。(期間限定でのアップですので必要な写真はダウンロードして下さい。)
https://photos.app.goo.gl/GBrwFa9XqaV8G3rG9



 タダ乗りではないにせよ、米国の提供する安全保障の「最大受益者
タダ乗りではないにせよ、米国の提供する安全保障の「最大受益者