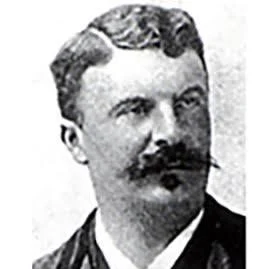昨年、台風来襲により急遽中止としたブナ立て尾根~読売新道~黒部湖をリベンジしました。天気は好天続きで、北アルプスの天水頼りの山小屋は、水不足となり、水の販売制限が1L/人、水のペットボトルは売り切れとなり、標高差1500mのブナ立て尾根は、水を5L担いで上がることになりました。裏銀座コースは好天が続くと予測されたため、昨年に比べて登山者多く、多くの登山者と話ができました。烏帽子岳~水晶岳までの稜線上からは、右側に、水晶岳~赤牛岳~読売新道のルートがよく見えて、また左側には、燕岳~槍ヶ岳までの表銀座の稜線がよく見えました。早朝はガスっていましたが、日の出とともに360度の大展望が続き、素晴らしい展望でした。3日目に水晶小屋から水晶岳・赤牛岳~読売新道を歩きましたが、前日良く見えた、歩きやすそうな稜線は、歩いてみると起伏が大きく思いのほか時間がかかりました。水晶岳~赤牛岳は大岩がゴロゴロして歩きづらく、読売新道は樹林帯に入る以前は、ザレ場・大岩ゴロゴロが続き、樹林
昨年、台風来襲により急遽中止としたブナ立て尾根~読売新道~黒部湖をリベンジしました。天気は好天続きで、北アルプスの天水頼りの山小屋は、水不足となり、水の販売制限が1L/人、水のペットボトルは売り切れとなり、標高差1500mのブナ立て尾根は、水を5L担いで上がることになりました。裏銀座コースは好天が続くと予測されたため、昨年に比べて登山者多く、多くの登山者と話ができました。烏帽子岳~水晶岳までの稜線上からは、右側に、水晶岳~赤牛岳~読売新道のルートがよく見えて、また左側には、燕岳~槍ヶ岳までの表銀座の稜線がよく見えました。早朝はガスっていましたが、日の出とともに360度の大展望が続き、素晴らしい展望でした。3日目に水晶小屋から水晶岳・赤牛岳~読売新道を歩きましたが、前日良く見えた、歩きやすそうな稜線は、歩いてみると起伏が大きく思いのほか時間がかかりました。水晶岳~赤牛岳は大岩がゴロゴロして歩きづらく、読売新道は樹林帯に入る以前は、ザレ場・大岩ゴロゴロが続き、樹林 帯に入ると太陽に照らされなくなり涼しくなりましたが、小さな岩や大木の根が湿気によりコケが生えて滑りやすく、何度か転倒して足を痛めました。読売新道は上りが少なく、ひたすら下る一方なので、コースタイム5時間のため、休憩時間を入れて4時間は切れるかと思っていましたが、意外に時間を要して、休憩時間を入れて5時間でした(実働は3時間30分)。奥黒部ヒュッテ~平の渡しまでは、早朝通過のためヘッドランプを付けての行動となりました。はしご・ザレ場の連続で、雪崩により壊れている箇所が3か所あり、下を流れる水の轟音が響きスリル満点でした。6月に68歳単独行の男性が落下し、亡くなったとのことで、緊張しながらの通過となりました。朝一番の渡し舟がAM6時出発であるため、3時起床、3時40分に奥黒部ヒュッテテントサイトを出発し、何とか1時間50分で平らの渡しに5:30到着。(船は6時15分発)黒部湖を横断する船は関西電力が無償で運航しているようで感謝です。平の渡し~ロッジクロヨンは、意外にも登り下りが多く、またハシゴ・ザレ場の連続で、こちらも3か所ほどは雪崩により崩れていました。黒部ダムまで来ると観光客が多く、ダムの上からは、はるか遠くに赤牛岳山頂が見えて感激でした。
帯に入ると太陽に照らされなくなり涼しくなりましたが、小さな岩や大木の根が湿気によりコケが生えて滑りやすく、何度か転倒して足を痛めました。読売新道は上りが少なく、ひたすら下る一方なので、コースタイム5時間のため、休憩時間を入れて4時間は切れるかと思っていましたが、意外に時間を要して、休憩時間を入れて5時間でした(実働は3時間30分)。奥黒部ヒュッテ~平の渡しまでは、早朝通過のためヘッドランプを付けての行動となりました。はしご・ザレ場の連続で、雪崩により壊れている箇所が3か所あり、下を流れる水の轟音が響きスリル満点でした。6月に68歳単独行の男性が落下し、亡くなったとのことで、緊張しながらの通過となりました。朝一番の渡し舟がAM6時出発であるため、3時起床、3時40分に奥黒部ヒュッテテントサイトを出発し、何とか1時間50分で平らの渡しに5:30到着。(船は6時15分発)黒部湖を横断する船は関西電力が無償で運航しているようで感謝です。平の渡し~ロッジクロヨンは、意外にも登り下りが多く、またハシゴ・ザレ場の連続で、こちらも3か所ほどは雪崩により崩れていました。黒部ダムまで来ると観光客が多く、ダムの上からは、はるか遠くに赤牛岳山頂が見えて感激でした。
(行動概要);七倉山荘~ブナ立て尾根~烏帽子小屋~水晶岳~赤牛岳~読売新道~黒部湖
7月30日(水); 自宅~(長谷川ピックアップ)→(上信越道)→麻績IC→信濃大町駅前ルートインホテル(泊) 車移動(280km;4時間)
7月31日(木); 宿泊先→信濃大町駅前~(裏銀座バス)~七倉山荘~(タクシー)~高瀬ダム⇒ブナ立て尾根登山口⇒烏帽子小屋⇒烏帽子岳⇒烏帽子小屋テントサイト(泊);
歩行距離(13km);コースタイム7時間10分(休憩時間2時間含む) 上り(1957m)・下り(492m)
8月1日(金):⇒烏帽子小屋テントサイト⇒三ツ岳⇒野口五郎岳⇒真砂岳⇒東沢乗越⇒水晶小屋(泊)
歩行距離(8.7km);コースタイム6時間31分(休憩時間1時間44分含む) 上り(837m)/下り(454m)
8月2日(土): 水晶小屋⇒水晶岳⇒温泉沢の頭⇒赤牛岳⇒奥黒部ヒュッテテントサイト(泊)
歩行距離(11.2km);コースタイム10時間45分(休憩時間3時間51分含む) 上り(436m)/下り(1836m)
8月3日(日) 奥黒部ヒュッテ⇒平ノ渡し場⇒ロッジクロヨン⇒黒部ダム→扇沢→信濃大町駅~
(車ピックアップ)~(大町温泉薬師の湯)→自宅;車移動(300km; 6時間30分)
歩行距離(15.1km);コースタイム7時間39分(休憩時間2時間16分含む) 登り1242m/下り1281m
(編集子)先に台湾遠征の記録を紹介したが、現役並みのアクティビティをキープしているグループの記録を紹介させてもらうことにした。その第一号である。聞くところでは5月にはまた、旧友を糾合してアルプス再踏破を計画しているとのこと。Boys, go for broke !