北原亜以子の「ぎやまん物語」(出版:文芸春秋。発行年:2014)を読む。著者、北原は1938年生まれだから、小生と同い年なのだが、残念ながら、2013年3月、心臓の病で亡くなった(享年75歳)。
ギヤマンとは、オランダ語(Diamant:ダイヤモンド)が語源のガラス製品のことだそうだが、ここでは手鏡の事を指している。それを狂言回しにしており、その特徴は、手鏡を擬人化していることだ。勿論、鏡に映る範囲では見ることは出来るが、喋ることは出来ない。ただし、聴くことは出来る。そこで、見たこと、伝聞を含めて聞いたことを読者に伝えると言う形で物語が進行して行く。そこには、手鏡の見解も含まれているが、それは、言うまでもなく、作家、北原自身の見解でもある。
話しは、ポルトガルの宣教師が持って来た手鏡を豊臣秀吉がオネダリして譲り受け、それを正室の北政所、於祢(おね)に渡すところから始まる。そこからその手鏡は、拾われたり、貸されたり、貰われたり、などして、以下の様に、転々と人から人の手へと渡って行く。彼らは、秀吉の側室お茶茶(淀殿)、徳川秀忠の正室お江、徳川家光の乳母お福、などなど、歴史上の人物で、夫々が一編の短編となっており、都合して16編から成り立っている。言い換えれば、全437頁に溜め込んだ簡略日本史と言っても差し支えなかろう。
そのなかで小生が最も記憶に残っているのは、以下の二つだ。
一つは、新選組による芹沢鴨の暗殺だ(「落日」の前篇・後編)。何故か、手鏡は芹沢鴨の手に落ちるのだが、その鴨に対し、手鏡、即ち、北原は、「鴨は多分、京都守護職の動きを尊攘派に漏らしていた。尊攘色の強い水戸で生まれ育ち、急進尊攘派として暴れ回っていた鴨が、近藤達と一緒に京に止まる理由は、幕府側の動きを尊攘派に伝える、それしかない」。つまり、鴨は討幕派だったと言うことになる。小生の認識不足もあろうが、この暗殺は、これまで、新選組内部の単なる内輪もめ、内ゲバだと思っていた。ところが、これを読むと、鴨は、新選組に潜り込んだ、今で言うスパイだったことになる。そうだとすると、沖田総司以下による暗殺行為は正当化されることになるわけだ。
もう一つは、「終焉」だ。手鏡を持っていた十四代将軍家茂の侍医である松本良順が、その診療所の手伝いに来ていた土肥庄次郎にその手鏡を渡す。何故なら、土肥が上野の山に立て籠もっていた彰義隊に参加することになり、手鏡を弾除けとして使うようにと渡したからだ。結局、新政府軍と一戦を交え、彰義隊は敗北。その際、流れ玉に当たって、手鏡は、最後に、上野の彰義隊と共に砕け散ってしまう。ここには、薩長政府に対する、江戸っ子の反骨心、反骨精神が垣間見え、物悲しさも漂わせ、そして、切なさをも感じさせ、山田風太郎の「幻燈辻馬車」を思い出させる。ここで、山田はもっと端的に薩長新政府に対するあからさまな嫌悪感を表明していた。この薩長政府に対する北原の反感は、東京・新橋の祖父からの椅子専門の洋家具職人の家に生まれたことと密接に関係しているのではないだろうか。格好良く言えば、江戸っ子としての矜持か。
なお、北原には、シリーズとして、人情ものの「深川澪通り木戸番小屋」(全:6巻)、元同心ものの「慶次郎縁側日記」(全:18巻)などがあるが、「慶次郎・・・」は主人公を高橋英樹がテレビでやっていたのでご覧になった方もおられよう。小生、人情ものは大好きなので、「深川・・・」は大変面白かった。


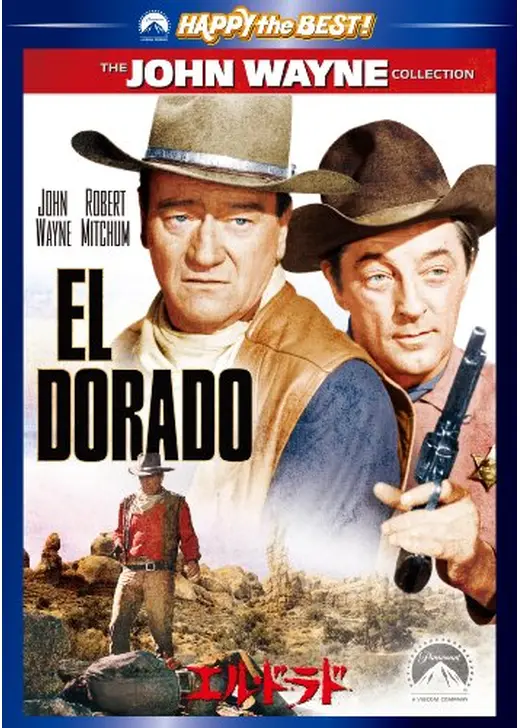





 シャ難民の子孫である。狂信的なシーア派の現在のイラン人とは異なる。全米にはシリア出身の人々も活躍している。多くはキリスト教徒(マロン派)やアラウィ教徒もいる。彼らは「ジハード」とは無縁で平和な民なのだ。 サクラメントは世界中の難民を大切にしてくれる進歩的な町である。カリフォルニア大学デービス校でSEとして勤務するペルシャ人の友人「ジャヒーン」、女性事務の「リラ」はシリア出身だった。「リラ」は母国シリアのパルミラ遺跡を誇らしげに語ってくれた。1993年に私がシリアを訪れた時の記録。
シャ難民の子孫である。狂信的なシーア派の現在のイラン人とは異なる。全米にはシリア出身の人々も活躍している。多くはキリスト教徒(マロン派)やアラウィ教徒もいる。彼らは「ジハード」とは無縁で平和な民なのだ。 サクラメントは世界中の難民を大切にしてくれる進歩的な町である。カリフォルニア大学デービス校でSEとして勤務するペルシャ人の友人「ジャヒーン」、女性事務の「リラ」はシリア出身だった。「リラ」は母国シリアのパルミラ遺跡を誇らしげに語ってくれた。1993年に私がシリアを訪れた時の記録。

