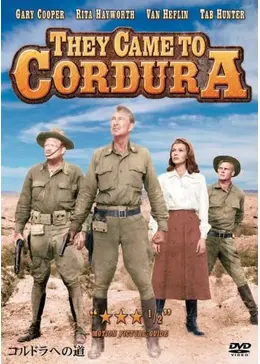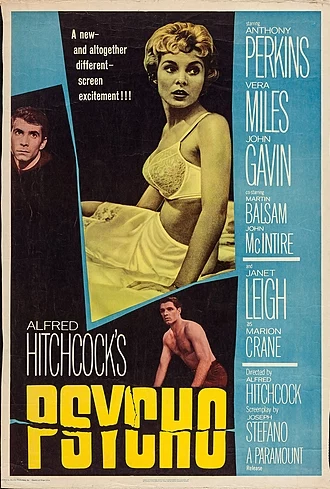2024年2回目の「月いち高尾」を2月28日(水)に実施。前日の台風並みの「春の嵐」一過の好天に恵まれ(今年の「月いち高尾」は誰が晴れ男・女なのか?2回とも幸先の良いスタート!)、北高尾の山稜、渓谷と裏高尾旧甲州街道沿いの五~六分咲きの梅見を満喫してきた。
2024年2回目の「月いち高尾」を2月28日(水)に実施。前日の台風並みの「春の嵐」一過の好天に恵まれ(今年の「月いち高尾」は誰が晴れ男・女なのか?2回とも幸先の良いスタート!)、北高尾の山稜、渓谷と裏高尾旧甲州街道沿いの五~六分咲きの梅見を満喫してきた。
<シニア・コース> 36年卒/鮫島さんが中心メンバーの「高尾の森つくりの会」の活動拠点となっている「高尾の森作業小屋」まで、「小下沢林道コース」散策。
・参加者(敬称略): 34/平松、36/鮫島、高橋、遠藤、大塚、吉牟田、37/矢部、39/蔦谷、三嶋、岡沢、多田、41/相川、46/木川、47/福本、平井、田端、伊川、関谷、63/斎藤、 BWV/大場 (20名)
10:12高尾駅<バス>⇒10:30木下バス停⇒木下沢梅林の梅を眺めながら⇒小下沢林道を和気藹々と談笑ながら散策⇒11:30高尾の森作業小屋 (昼食)<一般コースメンバーと合流>⇒12:20 参加者総勢32名が三々五々「小下沢林道」を下山⇒旧甲州街道沿いの梅を見ながら13:45摺差バス停⇒高尾駅 <一部健脚者は徒歩にて高尾駅> 文責:関谷誠
<一般コース>(夕焼け小焼け⇒北高尾黒ドッケ⇒杉ノ丸⇒小下沢作業小屋⇒木下沢梅林)
(1)具体的行程
(アクセス)高尾駅北口バス停8:35⇒9:01夕焼け小焼けバス停
夕焼け小焼け園地250m9:10⇒(1時間20分)⇒黒ドッケ489m10:30⇒(15分)⇒10:45杉の丸587m11:00⇒(30分)⇒狐塚峠⇒(15分)⇒11:45小下沢小屋(昼食)12:20⇒(40分)⇒日影13:00⇒13:20摺差(峰尾豆腐店)13:45⇒14:00高尾駅北口バス停
(2)参加者12名(敬称略()内は昭和の卒年)
(39)堀川義夫(42)下村祥介、保屋野伸(43)猪俣博康(44)吉田俊六(45)徳尾和彦(46)村上裕治(48)佐藤充良(50)丸満隆司(51)羽田野洋子、保田実、斎藤邦彦
(3)行程概要
2名がコロナ感染のため欠席だったが、予定通りのバスに無事に参加者全員が乗車し、ボンネットバスやポニー牧場のある「夕焼け小焼け園地」から登山道に入る。取付きの急登を30分、息を切らせて登りベンチのある台地で小休止、ここまでかなりのスピードで上がってペースを作ることが出来た。
少しだけ雪の残る距離の長い小さい登り下りを幾度か繰り返し黒ドッケを過ぎ杉の丸まで一気に到達する。地図上のコースタイムを大幅に短縮したので昼食は小下沢小屋まで足を伸ばすこととした。下りも快調に北高尾山稜を進み狐塚峠から小下沢小屋に向かって下る。小屋のかなり上から小屋の周りの人影が見えたので「おーい!」と声を掛けたが返事がない。われわれのグループではなかったのかと思ったが、シニアチームからしてみるとこんなに早く降りて来るとは思ってもみなかったとのことだった。
2グループ32名全員が揃って小下沢小屋の前で昼食を摂るというこの会にとって初めての大イベントとなり、会話も弾んだ。昼食後は三々五々に木下沢梅林で観梅を楽しみ、摺差の豆腐店で寄せ豆腐を味わった人も多かった。
 打ち上げはいつもの「天狗飯店」、2/9放送のテレビ番組の話題にも花が咲く。話題も豊富でいつにも増して盛り上がった「月いち高尾」でした。
打ち上げはいつもの「天狗飯店」、2/9放送のテレビ番組の話題にも花が咲く。話題も豊富でいつにも増して盛り上がった「月いち高尾」でした。
文責:斎藤邦彦
<「天狗飯店」懇親会> (28名参加) 63/斎藤伸介の加山雄三ヒット曲数々のワンダー・高尾バージョン替え歌のウクレレ・コンサートで大いに燃え上がった。
注:山行中に話題になった「黒ドッケ」の由来
諸説あるようですがドッケは尖った場所を指す言葉で「突起(トッキ)」が変化したもののようです。奥多摩にはこの地名が多く「三つドッケ(=天目山)」や「芋木のドッケ」などの地名が残っています。