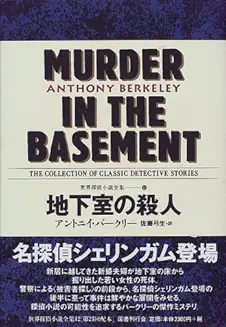テレビで最近睡眠に関するニュースが多くないですか? 日本人の平均睡眠時間は約7時間。これは諸外国に比べると少し短いようです。そのせいかJRなどの乗ると、座っている人は全員 スマホをいじっているか寝ているか。まあ目の前に高齢者などが立った時に狸寝入りをきめこむ若人もいるけどね。
不眠には入眠障害(寝つきが悪い)と、頻回に目が覚めるもの(途中覚醒)があります。
皆さんは寝つきは良いですか? 夜中に何回ぐらい排尿で起きるかな? 私も最近以前よりは寝つきが悪くなりました。但し、夜中には1回 眼が覚めるか、全然起きないかのどちらかですね。夕食時にビールや水分をたくさん飲んだ時以外は、夜中は起きないことが多いですね。しかしこれは例外的で、70歳を過ぎたら1-2回夜中に排尿で起きるのは普通かな。これは余り心配しなくていいでしょう。排尿の後、またすぐグッスリ眠れるならば。
この不眠は心筋梗塞や脳卒中発症と関係があることが医学的にはほぼ常識化しており、最近では心不全やアルツハイマー病になる確率も高いことが分かってきました。もっとも毎日9時間以上寝るのも認知機能障害には問題という報告もあります。7-8時間の睡眠が皆さんのお年では最適かな。子供さんはもっと寝ていいと思いますが。
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」って聴いたことありますよね。睡眠中、大イビキをかき、良く観察すると途中で息が数十秒ぐらい止まる方、パートナーにそれを指摘されたら、是非呼吸器の専門家に相談してください。これも不眠の原因の一つです。舌根が睡眠中に喉に落ち込み易かったり 肥満やあごの形・扁桃腺の肥大など原因は様々ですが、一般的にこれらの方は血液が固まりやすい傾向があり、脳や心臓の血管が詰まる可能性が高いのです。
じゃ、眠れなかったり、一晩に3-4回以上も起きてしまうのはどうしたら良いかって?
一度、懇意の主治医に相談することでしょうね。SASならCPAPという装具をつけて良く成った方が沢山います。SASもなく、頻尿のみで起きる方は、まず泌尿器科で前立腺や女性の場合は膀胱などに異常がないか診てもらってください。テレビで宣伝している漢方薬は夜間頻尿には効かない人も多いようですが。SASや膀胱・前立腺にも異常がない場合、医師は睡眠薬を勧めるかもしれません。しかしこれも考え物です。従来の睡眠薬の多くは、無理に脳の機能を抑え込んで眠らせるものもが多く(これは一寸誤解を招く表現ですが,分かりやすく表現しました)長期使用は認知機能を抑えてしまうとも言われています。すなわち、ボケやすくなるわけです。最近、オレキシン受容体拮抗薬という新薬が出てきました。これはそのような有害事象は出にくいと言われていますから、かかりつけ医から従来型の睡眠薬を長期に貰っている人は良く相談してください。
まあ、寝酒として強めのアルコールをほんの少量飲むのはアリかもしれませんね。しかしビールやお湯割りをたくさん飲めば、また排尿で起きてしまいますよ。
「眠れなければ我慢して眠らなければいい、眠って死んだ方はいるが眠れないで死んだ方はいないよ」と時々、冗談で神経質な患者さんには申し上げますが、実は非常に稀なスローウィールス感染症という病気(もう過去の病気だと忘れられている狂牛病もその一つです)の中に「致死性家族性不眠症」という病気もあります。これはホントに眠れないで死んでしまう病気ですが、この病気は非常に稀で、私が20年以上前に日本の第1例目を米国雑誌に発表して以来、まだ日本からは2例目が出ていないくらい稀有な病気ですから心配はいりません。
そんなことより、長く続けた昔からの睡眠薬から脱皮できず。新しい薬を渡されても、効かないと自分で決めこんで、古くからの薬にこだわる人のことが心配です。年をとると意固地になる人が多いからね。






![荒野に生きる [Blu-ray]](https://i2.wp.com/m.media-amazon.com/images/I/51gRdT9eLEL._SL500_.jpg?w=525&ssl=1) 「荒野に生きる1971」は、舞台・時代は19世紀開拓初期の米
「荒野に生きる1971」は、舞台・時代は19世紀開拓初期の米