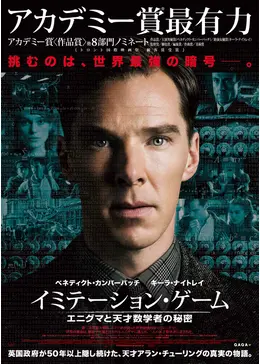来年、創部90周年を迎えるKWVで育った我々ワンダラーの山登り、山歩きに対する情熱は老若男女失せることありませんが、現実は厳しく、体力・足腰の衰えを如何とも隠せない老齢世代、一方で、それなりの体力を維持しながら、何とかごまかし得る若年老齢世代等々、幅広い層が参加・楽しめるイベントの企画は、KWV三田会としても大きな課題のようです。 この「月いち高尾」の会は、発起人の36年「ナンヤカンヤ」会の皆さんの参加がおぼつか無くなった時点で、自然消滅させても良いのかも知れません。しかし、バリバリの若年老齢世代の参加が増え始めている昨今、又、「テング飯店」での後の祭り懇親会も店が貸し切り状態となる盛り上がりを呈しており、何とかこの会を継続できないかと悩み、思案する三代目世話人です。そこで、今回、新たな試みとして、「高尾山」山域をゆっくりと自然に触れながら、仲間とワイワイガヤガヤ、体力的負担の軽い山歩きの「シニア―」向けプランと、それなりにハードな登山を楽しめるプランの2本立てとし、下山後は、「テング飯店」に集結とのプランを企画しました。
<以下、敬称略>
(シニア―・コース) 34/船曳夫妻、36/遠藤、中司、高橋、吉牟田、鮫島、39/蔦谷、三嶋、40/藍原、41/久米(コブキ)、43/保屋野、44/吉田、47/平井、関谷 <14名>
(南高尾7サミット・コース) 39/堀川、42/下村、44/安田、46/村上、49/長山、50/実方、丸満、51/斎藤、五十嵐、羽田野、59/後藤、BWV/大場 <12名>
10:00 京王線「高尾山口」集合 (1) 10:15清滝発ケーブルカー (2) 保屋野/久米/吉田 6号路琵琶滝コース 11;30 高尾山山頂 昼食
秋の遠足シーズンで、山頂はビニシーを所狭しと広げ、美味しそうな手作り弁当をほおばる小学生、幼稚園児で賑わっており、我々年寄りはそれを楽しく眺めながら、多少のエネルギーを充填出来たかな!この子らに見惚れたのか、何と二人の御仁が昼食をとった石の腰掛にスマホを忘れ、下山途中の薬王院近くで気付き、慌てて山頂に引き返すハプニングがあった。園児を引率していた保母さんだったのではないと推定されたが、何と、バラバラに座っていた場所に置き忘れた2台が揃って、目の付くところに、並べて置いといてくれており、事なきを得、スマホが命と豪語する御仁の喜び様と云ったら! ちゃんと置いといてくれた日本人の美徳を一同称賛。
下り:
・本隊: ケーブルカーで清滝に下山
・遠藤/保屋野/関谷: 1号路から、途中、金毘羅尾根を下り高尾駅へ
平均年齢82歳とは思えない元気なシニア―、足腰が多少覚束ない方も見受けられたが、口の方は相変わらずお元気そのもの、体調不良、事故等のない、9月末とは思えない 暑い中での汗をかいての楽しい秋のワンデルングでした。

JR相模湖駅(八王子駅北口行き)8:39⇒(バス16分)⇒8:55大垂水峠9:00⇒(30分)⇒9:30①大洞山536mオオボラヤマ9:40⇒(50分②コンピラ山③中沢山494m)⇒10:30見晴台10:40⇒(50分④入沢山⑤泰光寺山)⇒三沢峠11:30⇒(30分⑥榎窪山420m)⇒12:00⑦草戸山364m(昼食)12:35⇒(1時間10分)⇒13:45四辻13:50⇒(20分)⇒14:10高尾山口駅
・朝は全員が予定通り相模湖駅のバス停に集合、バスで大垂水峠へ向かい下車後、大垂水歩道橋から出発しました。軽快な足取りで登りをこなすとひと汗かいたころにこの日の最高地点大洞山(オオボラヤマ536m)に到着し、さらに引き続きコンピラ山、中沢山を通過しこのコース最高のビュースポットである見晴台からの丹沢方面の眺望を楽しみました。
・セカンドを歩く堀川さんの歩きがとても早くトップを歩く五十嵐さんが煽られっぱなしで予定より20分も早く最終の第7のピーク草戸山に到着、ゆっくりと昼食を摂りました。・草戸山から高尾山口までは小さなアップダウンを繰り返しながら緩やかに下っていく長いコースでしたが、いつの間にか堀川さんがトップになってパーティをリードし快調に高尾山口まで下りました。
(編集子)今回は別報した通り、メンバー(当会第二代世話役)堀川義夫君の100名山登頂を祝して、二次会において記念のプレートを贈呈した。次はだれになるか、興味深々である。ホリ、おめでとう!
関谷君報告原文にある ナンヤカンヤ会 というのは ナンカナイ会という光輝と栄誉ある(実社会ではときどき不都合に遭遇することもあることを体験ずみではあるが)名称の誤記であることを付記。本件は同氏あて配達証明つきにて訂正を申し入れ済み。
尚、写真は多数寄せられていて掲載が困難であるので、参加者には撮影者から送られているグーグルファイルをご参照されたく、本稿には代表例のみを転載させていただく。
(久米)斉藤氏の素晴らしい写真集も楽しく拝見いたしました。やはり「南高尾7サミットコース」楽しそうですね。参加したかったです。でも体力に自信が無くて琵琶滝コースを歩きました。
永遠の少年、保谷野氏と、ずん六植物学者と教養深い山行を楽しみました。まだまだ夏の花も残っていてシュウカイドウなど見事な花を見ながら、ずん六先生の解説付き和歌まで飛び出して「自然教室」に参加しているような気分の中々教養深い山行でした。行き交った保育園の生徒達小学5年生、皆驚くほど元気で励まされました。
天狗の飲み会も無事スマホが見つかったこと、堀川さんの100名山達成のお祝いと楽しい会でした。色々お世話になりました。
 当時91歳のクリント・イーストウッドが監督デビュー50年40
当時91歳のクリント・イーストウッドが監督デビュー50年40 二人の絆ガ胸にこみ上げる。助演男優賞の闘鶏、
二人の絆ガ胸にこみ上げる。助演男優賞の闘鶏、