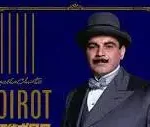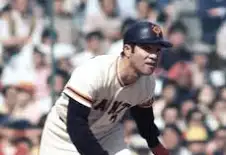最近、以下のクリスティーの探偵小説を読んだ。
「ゼロ時間へ」(Towards Zero)1944年。翻訳:三川 基好。早川書房(クリスティー文庫)。
「カリブ海の秘密」(A Caribbean Mystery)1964年。翻訳:永井 淳。早川書房(クリスティー文庫)。
「復讐の女神」(Nemesis)1971年。翻訳:乾 信一郎。早川書房(クリスティー文庫)。
 その切っ掛けは、ネット上で、クリスティーの誕生日(1890年9月15日)を祝った画面で、「あまり読まれていないクリスティーの傑作」(正確にどんな題名だったのか想い出せない)を覗いたことからだった。この他に、「死との約束」、「アガサ・クリスティー自伝」、「蒼ざめた馬」が挙げられていた。
その切っ掛けは、ネット上で、クリスティーの誕生日(1890年9月15日)を祝った画面で、「あまり読まれていないクリスティーの傑作」(正確にどんな題名だったのか想い出せない)を覗いたことからだった。この他に、「死との約束」、「アガサ・クリスティー自伝」、「蒼ざめた馬」が挙げられていた。
「ゼロ・・・」。殆どの探偵小説は殺人事件で始まり、警察、或いは、私立探偵が駆けつけて、犯人探しを始めるのがその流れだ。ところが、ここでは、ゼロ時間(殺人)に向かって様々な要因があり、その結果として後半に殺人が起こる新形式となっている(具体的に、375頁ちゅうの209頁で殺人が起こる)。つまり、誰が加害者で誰が被害者になるかが話の焦点となり、お馴染みのポワロもマープルも登場せず、探偵役はバトル警視となっている。しかし、1944年の発表以来、クリスティーは二度とこの新しい形式を試みておらず、その意味では、この新形式は失敗だったと見做すことの方が正解だろう。
「カリブ・・・」。これは、何もカリブ海に秘密があると言う訳ではなく、カリブ海で起こった殺人事件と言った方が正しい。そのカリブ海に静養に来ていたマープルが、かなり衰弱した老人の大富豪と共に殺人事件を解決する話で、これは真っ当な探偵小説なのだが、そのミソは大富豪の存在だ。
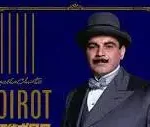 「復讐・・・」。「カリブ・・・」の後日談で、その大富豪が亡くなり、マープルに後事を託す。ところが、その後事が、具体的に何を意味するかの指示が全く不明なことから、それが何かを探ることから話しは始まって行く。従って、458頁にも及ぶ大作となっており、何事も起こらない時間が続いて行くことから、いささか退屈と思われる読者も出て来ることだろう(小生は、クリスティーの、いわゆる、ストー
「復讐・・・」。「カリブ・・・」の後日談で、その大富豪が亡くなり、マープルに後事を託す。ところが、その後事が、具体的に何を意味するかの指示が全く不明なことから、それが何かを探ることから話しは始まって行く。従って、458頁にも及ぶ大作となっており、何事も起こらない時間が続いて行くことから、いささか退屈と思われる読者も出て来ることだろう(小生は、クリスティーの、いわゆる、ストー リー・テリングに大いに堪能しており、この3冊の中では最も面白かった)。なお、「復讐の女神」とはマープルのことを指している。
リー・テリングに大いに堪能しており、この3冊の中では最も面白かった)。なお、「復讐の女神」とはマープルのことを指している。
結局のところ、クリスティーには敵わない。いずれも、凡そ犯人らしからぬ人物が犯人であって、犯人を当てることは出来なかった。だからと言って、傑出したトリックがある訳でもなく、「復讐・・・」以外は、さして興をそそられる内容ではなかった。
 しかし、ここからが肝心なところだが、「カリブ・・・」の解説者、穂井田 直美が言っているように、クリスティーの最大の魅力は、「エンターテインメントなストーリー作りに長けていること、加えて人物造形のうまさや、心理描写の巧みさなど」、に尽きるのではないか。この点では、並みの探偵小説を遥かに凌駕しており、極めて傑出している。乱暴な言い方だが、その話しの進み方次第では、誰が真犯人かは、もうどうでもよくなってしまうのだ。極端に言えば、クリスティーにとって殺人事件は「刺身のつま」程度のものに過ぎなかったのではないか、との妄想も浮かんでくる。
しかし、ここからが肝心なところだが、「カリブ・・・」の解説者、穂井田 直美が言っているように、クリスティーの最大の魅力は、「エンターテインメントなストーリー作りに長けていること、加えて人物造形のうまさや、心理描写の巧みさなど」、に尽きるのではないか。この点では、並みの探偵小説を遥かに凌駕しており、極めて傑出している。乱暴な言い方だが、その話しの進み方次第では、誰が真犯人かは、もうどうでもよくなってしまうのだ。極端に言えば、クリスティーにとって殺人事件は「刺身のつま」程度のものに過ぎなかったのではないか、との妄想も浮かんでくる。
現に、クリスティーの最初の習作長編は未出版の「砂漠の雪」(1906年。16歳の時)であって、これは探偵小説ではなく、後に(1930年)、メアリー・ウェストマコット名義で出された普通の小説の先駆けとなるものだった。探偵小説は、篤志看護婦として陸軍病院に勤務していた1914年(24歳)から書き始めており、それが、後の「スタイルズ荘の怪事件」となって、1924年に出版された。
今、「・・・自伝」を読み始めているが(序の24頁まで)、なにしろ改行が殆どなく頁が活字で埋まっており、その上、上巻は532頁、下巻は529頁と1000頁を超える代物なので前途多難だ。それにしても、クリスティーの記憶力にはおっ魂消るしかない。
(小田)お久しぶりのアガサ·クリスティですね。ヤッコさんも殆ど読まれているようですが、私も’16年にイギリス南部(デヴォン)のアガサゆかりの場所を訪ねた前後あたりに色々読みました。
最近は、面白いTVのない時に録画してあるポアロやミス·マープルを見直しています。菅原さんが今回読まれた3作は、TVでは全て私の大好きな”ミス·マープル”物ですね。TVは本と内容が少し違いますが、綺麗なバラいっぱいの庭園や、コッツウォルズのような景色が楽しめるのがいいです。
登場人物が多く、最後の謎解きで分からなくなりますが、ご指摘のように普通の小説としても楽しめますね。知らない人物からバスツアー券を受取り集まった人々が、一緒にバスでハイキングをしたり、邸宅や古い修道院を巡る《復讐の女神》が好きです。共通して人気が高いのは、《予告殺人》のようです。
✩クリスティーの《火曜クラブ》を思い出させる、イギリスで人気の、リチャード・オスマンの《木曜殺人クラブ》。同じ施設に入居している老人たちが、暇つぶしに未解決事件を解決していく…を読んでみたいと思います。
(編集子)先日書いたが、こちらは目下、クイーン再訪、を始めたところだ。まだまだ前途遼遠、なのだが、このスガチュー論でなるほど、と思い当たったことがある。エンタテインメント性、ということである。クリスティは生前、毎年クリスマスには読者が(今年のプレゼントは何か)と新作を心待ちにしていた、という。探偵役がポアロにせよミスマープルにせよタペンスにせよ、だれにでも好かれる好人物の側面を持っているのもその理由だったのだろう。対するにクイン物のエラリーは学歴と博学をひけらかし、片眼鏡をかけた偏屈な学者はだしであり、もう一人の同時代人ヴァン・ダインの主人公ファイロ・ヴァンスにいたってはことあるごとに美術や文化の博学ぶりを見せつける、とても友人にしたいとは思わない衒学徒で、まともな市民の仲間とは思えない人物として描かれる。
そういう主人公を持ってきたので、話自体が当時の知識階級を読者に想定したものになっていて、確かにミステリとしての技術論は素晴らしいが、どうしても一般の人がクリスマスに期待する雰囲気の作品にはならない。このあたり、万事につけて兄貴分の英国の鷹揚な雰囲気に、ともかく力で対抗する米国人気質の表れなのかもしれない。”エンタテインメント性” を欠き、論理だけを振り回すニュ ーヨーク発の話が、より日常性を基盤にした、東海岸文化の向こうを張る西海岸での、ハードボイルドミステリの誕生につながったのだろう、と改めて思う。
ーヨーク発の話が、より日常性を基盤にした、東海岸文化の向こうを張る西海岸での、ハードボイルドミステリの誕生につながったのだろう、と改めて思う。
ところでポアロ役だが、小生が特に気に入っているのは ”ナイル殺人事件” でのピーター・ユスチノフなんだが、賛同者いない?
 (We’re no Angels) 1955年公開)。共に封切りより随分月日が経って(25年近く
(We’re no Angels) 1955年公開)。共に封切りより随分月日が経って(25年近く した。 ポアロ役では「地中海殺人事件」(1982年)にも出演していました。 ピーター・ユスチノフは「クオ・ヴァディス」(1951年)、「
した。 ポアロ役では「地中海殺人事件」(1982年)にも出演していました。 ピーター・ユスチノフは「クオ・ヴァディス」(1951年)、「 ことはもうないだろうが、これでユスチノフがいたらどうなっていただろうか。2017年版のポアロはケネス・プラナーで、ほかのメンバーもぐっと若返っている(当たり前だが)のを感じる。
ことはもうないだろうが、これでユスチノフがいたらどうなっていただろうか。2017年版のポアロはケネス・プラナーで、ほかのメンバーもぐっと若返っている(当たり前だが)のを感じる。