ま、日本広しといえども知ってる人はまずいねえだろうなあ、と浅はかな優越感を持って書いている。
数日前の読売に、”遺作になった占領日記” という記事が出た。ウクライナでロシア化に抵抗した文学作家バクレンコがロシア占領の現実を書き残した秘密の日記をロシア軍に連行される直前、庭に埋めて隠した。そのことを本人から知らされていた父親に聞かされた、ビクトリア・アメリーナという女性作家が桜の木の下から掘り出した。最後のページは 全てはウクライナになる!勝利を信じている! と書かれてあったという。アメリーナはこの本の出版に全力を挙げ、すでに欧州各国で出版されているが、彼女自身もまた、ロシア軍のミサイル攻撃で亡くなったというのだ。
こういう悲劇はおそらくウクライナ、あるいはロシアでも数多くあるのだろう。他国の話ではあるが、形こそ違え、日本にも同じような過去を持つ人がおられるはずで、とにかくもこの戦争が終わる日を待ち続けるしかない。
こういう悲劇を題材に軽々しく文章を書くことは慎むべきなのだが、この記事の一節にある、桜の木の下、というところが気になった。バクレンコはその場所をどのように伝えていたのだろうか。そう思ったときに、ひらめいたのが表題にした リンバガスカ という暗号である。不謹慎と怒られるのを覚悟で、思い出したことを書く。
 小生の小学生から中学1年の間位に、当時続々と復刊されていたのが戦前の少年倶楽部誌に連載されていて、終戦直後はGHQの方針で復刻を許されていなかった、冒険物語のかずかずだった。いわく山中峯太郎、久米元一、南洋一郎に野村胡堂。”亜細亜の曙”(テレビ番組にもなったそうだが知らなかった。ヒーロー本郷義昭いわば大日本帝国版ジェームズ・ボンド、なんてあこがれたもんだ)とか、”敵中横断三百里” とか、いまではタイトルもあやふやだが、いろんな本をよみふけったものだ。その中であらすじも明確に覚えているのが野村胡堂の ”地底の都” という一編。富士山麓のある場所に、日本史に記されていない過去の都がうずもれているという発見をめぐって、その秘密を知っている考古学者が誘拐される。考古学者春日万里を救出しようと主人公の
小生の小学生から中学1年の間位に、当時続々と復刊されていたのが戦前の少年倶楽部誌に連載されていて、終戦直後はGHQの方針で復刻を許されていなかった、冒険物語のかずかずだった。いわく山中峯太郎、久米元一、南洋一郎に野村胡堂。”亜細亜の曙”(テレビ番組にもなったそうだが知らなかった。ヒーロー本郷義昭いわば大日本帝国版ジェームズ・ボンド、なんてあこがれたもんだ)とか、”敵中横断三百里” とか、いまではタイトルもあやふやだが、いろんな本をよみふけったものだ。その中であらすじも明確に覚えているのが野村胡堂の ”地底の都” という一編。富士山麓のある場所に、日本史に記されていない過去の都がうずもれているという発見をめぐって、その秘密を知っている考古学者が誘拐される。考古学者春日万里を救出しようと主人公の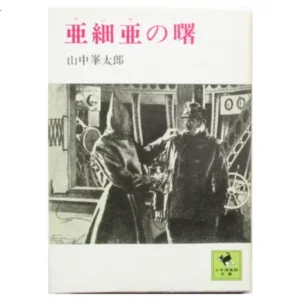 少年二人と妹が活躍するのだが、その過程で、彼らの手元に博士の書いた手紙が届く。ただ少年たちには末尾にかかれた リンバガスカ という意味が分からない。二人は優等生と元気少年の従兄弟同士、その優等生のほうが、これはおじさんの名前 春日万里 をさかさまにつづったものだ、と見抜き、わざわざさかさまにしたのは、この手紙に書かれているてがかりをすべて逆に解釈せよということだ、と見抜く。この後は三人に味方する名探偵に鬼警部、というお定まりで大団円になるんだが、ひょっとするとウクライナの作家もこんな秘密文を書き残しておいた、なんてこたあねえだろうなあ、と思った、という次第。ウクライナで呻吟されている人たちには不謹慎で申し訳ないとは思うのだが。
少年二人と妹が活躍するのだが、その過程で、彼らの手元に博士の書いた手紙が届く。ただ少年たちには末尾にかかれた リンバガスカ という意味が分からない。二人は優等生と元気少年の従兄弟同士、その優等生のほうが、これはおじさんの名前 春日万里 をさかさまにつづったものだ、と見抜き、わざわざさかさまにしたのは、この手紙に書かれているてがかりをすべて逆に解釈せよということだ、と見抜く。この後は三人に味方する名探偵に鬼警部、というお定まりで大団円になるんだが、ひょっとするとウクライナの作家もこんな秘密文を書き残しておいた、なんてこたあねえだろうなあ、と思った、という次第。ウクライナで呻吟されている人たちには不謹慎で申し訳ないとは思うのだが。
 亜細亜の曙、の挿画は当時売れっこだったという椛島勝昭のペン画だそうだ。戦後のペン画、いわば現代っ子のマンガ本のはしりとして記憶にあるのが小松崎茂だ。代表作 地球SOS は苦労して探し出して、手元にある。空魔エックス団、とか ハリケーンハッチ、なんてもあったな。同じころ興奮した、これは小松崎ではないが、歴史もので熱狂したのが怒涛万里を行くところ、というのも思い出した。これは作者も覚えていないので、復刻版もまずないだろうが。山川惣治の少年王者、は少し遅れて登場した、これも名作だった(KWV36年卒同期の山室修のニックネーム、ザンバはこの作品に登場する大男の名前である)。
亜細亜の曙、の挿画は当時売れっこだったという椛島勝昭のペン画だそうだ。戦後のペン画、いわば現代っ子のマンガ本のはしりとして記憶にあるのが小松崎茂だ。代表作 地球SOS は苦労して探し出して、手元にある。空魔エックス団、とか ハリケーンハッチ、なんてもあったな。同じころ興奮した、これは小松崎ではないが、歴史もので熱狂したのが怒涛万里を行くところ、というのも思い出した。これは作者も覚えていないので、復刻版もまずないだろうが。山川惣治の少年王者、は少し遅れて登場した、これも名作だった(KWV36年卒同期の山室修のニックネーム、ザンバはこの作品に登場する大男の名前である)。
あの頃の少年たち、つまり俺たちがこれらの子供向けSF小説の上で熱狂した”未来” は21世紀だった。よくわからないけどいい時代になるらしい、と信じたものだ。それが今。そうか、世の中はこうなるんだ、と興奮したもんだが、いまだに領土争いだの宗教論争なんかで戦争が起きてる。まったく進歩してねえじゃねえか。あらためて本稿のきっかけになったウクライナの悲劇に心が痛む。




















