
2024年の本作では、真田広之が『ラストサムライ』(
ヨーロッパとはまったく違う社会制度や生活習慣に驚きながらも、
映画の時代は、天下を治めていた太閤豊臣秀吉亡き後( である戸田文太郎(細川忠興)の妻で、
である戸田文太郎(細川忠興)の妻で、
細川ガラシャ:
明智光秀の三女で、
ニュージーランドで生まれ、東京で育つ。
・石堂和成[石田三成] – 平岳大

旧き友集い語ろうは 過ぎし日の旅山の想い (投稿は著者あてメールでお願いします)

2024年の本作では、真田広之が『ラストサムライ』(
ヨーロッパとはまったく違う社会制度や生活習慣に驚きながらも、
映画の時代は、天下を治めていた太閤豊臣秀吉亡き後( である戸田文太郎(細川忠興)の妻で、
である戸田文太郎(細川忠興)の妻で、
細川ガラシャ:
明智光秀の三女で、
ニュージーランドで生まれ、東京で育つ。
今朝の冷え込み現在の外気温マイナス2度となっています。日中は寒気も次第に緩んで日差しの温もりを感じれるかもしれません。
一昨日大泉から事務所に帰る際、甲府盆地の明かりの向こうに富士山が見えました。すっかり冬の装いですね. 長坂小荒間地区の富士見坂周辺からの冬姿です。
読売新聞のシリーズ 時代の証言 が今回は加山雄三(池端直亮)だった。上原謙 という戦中から戦後にかけて、日本の映画界を代表する二枚目スターの長男として生まれた彼は小生と同じ昭和12年生まれ。僕は満州からの引き揚げ組だが、帰国した時点ではだいぶ衰弱していたらしく、用心深かった母は帰国後すぐ復学させず、ほぼ半年遅れで小学校へ戻ったので、同い年よりは一学年遅れであった。もしこのことがなければ、彼とは慶応高校で同期だったはずだから、多分知り合いになり、(おい、池端ア)なんていう仲になっていたかもしれない。KWVの1年先輩(つまりひょっとしたら同期だったはずの)の何人かが彼と高校時代に交友があって、その関係で一度、蔵王で彼と遭遇、華麗なスキーをみたこともある。そんな因縁があって、今回の31回にわたった連載は自分の時代の思い出、と思いながら完読した。
映画スターの息子、という環境でいろいろ難しい問題もあったのだろうが、高校入学以前、というより幼少のころからミュージシャンとしての天分に恵まれ、一方ではその後ヨットを自作するまでの才能豊かな少年だったことが書かれている。何かといえば上原謙の息子、とみられることに反発して高校時代は硬派で通そうと髪を五分刈りで通してスキーに熱中し、妙高高原ではパトロールをやっていたし国体にも出場したというから、当時赤倉燕に通い詰めていた僕らとひょっとしたらゲレンデですれ違っていたかもしれないし、レベルの違いはあれ、同じような生活だったのだろうと親しみを覚える。この時代、僕らを引き付けた音楽シーンのことどもは曲名をきくだけでも懐かしい。大学卒業にあたって就職を考えた時点で意に反するような形で俳優になった、いうのも、同じ時期、あるハプニングがきっかけで新聞記者になろうという意思をなくしてサラリーマン生活を選んだ、僕自身のありように引き比べて感ずることが多かった。
俳優、ミュージシャンとしてのサクセスストー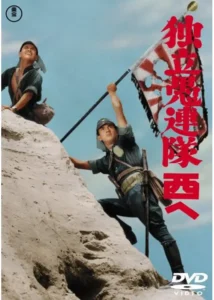 リーは今更いうまでもない。ただ、彼の映画の中核として触れられている若大将シリーズは、例によって起きてしまった天邪鬼症状で、一本も見ていないが、椿三十郎の若武者ぶりは素晴らしかったし、”独立愚連隊西へ” での活躍も面白かった。しかしこの新聞コラムを続けて読もうと思い立ったのは、高校同窓、という親近感もさることながら、その第一回目の見出しが100歳まで生きる宣言、となっていたからだ。そしてそのために生活態度をあらためている、という意気込みに賛同したからでもある。先輩にあたるわけだから、池端さん、と言わなければならないのかもしれないが、お互い他人さまから見れば恵まれた環境を生きてきた同時代人として、俺だって100歳まで生きてやらあ、という意気込みにさせてくれた読み物だった。
リーは今更いうまでもない。ただ、彼の映画の中核として触れられている若大将シリーズは、例によって起きてしまった天邪鬼症状で、一本も見ていないが、椿三十郎の若武者ぶりは素晴らしかったし、”独立愚連隊西へ” での活躍も面白かった。しかしこの新聞コラムを続けて読もうと思い立ったのは、高校同窓、という親近感もさることながら、その第一回目の見出しが100歳まで生きる宣言、となっていたからだ。そしてそのために生活態度をあらためている、という意気込みに賛同したからでもある。先輩にあたるわけだから、池端さん、と言わなければならないのかもしれないが、お互い他人さまから見れば恵まれた環境を生きてきた同時代人として、俺だって100歳まで生きてやらあ、という意気込みにさせてくれた読み物だった。
小泉さんに感想を詳しく書いて頂いた「ロイ・ビーン」を初見でみました。
私はポール・ニューマンは「傷だらけの栄光」「熱いトタン屋根の ン」(1972年)は、絶頂期の彼の代表作
ン」(1972年)は、絶頂期の彼の代表作
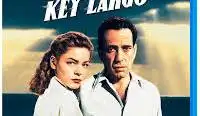 ジョン・ヒューストンという監督は“鬼才“と
ジョン・ヒューストンという監督は“鬼才“と
 翻って「ロイ・ビーン」にもポーカー賭博シーンが2~3回出てき
翻って「ロイ・ビーン」にもポーカー賭博シーンが2~3回出てき
折角のP.ニューマン主演の映画でしたが残念でした。率直な感想
(小泉) 飯田さんの言われること、もっともと思うことが多々あります。小
の内容を紹介するだけの、個々のエピソードをごたごた書きすぎて
(編集子)この人(ニューマン)のことは良く知らないので見当はずれかもしれないが、基本的にセーブ劇向きの人じゃなかったと思うな。スマートすぎるというか、うまく言えないんだが、いつも冷笑的な、都市人特有の感じが抜けない気がする。

9年ぶりに、京都の紅葉をJRのツアー(往復新幹線とホテル京阪2泊のみ)で楽しんできました。今年の紅葉は夏の猛暑でイマイチとの不安もありましたが、色づきはまあまあだったと思います
名所の、光明寺、真如堂、常寂光寺、北野天満宮のモミジ宛、そしてNo1の永観堂、素晴らしい紅葉でした。また、同期の,京都にマンションを持っているモツ(田中ひろみさん)から紹介された「智積院」が今回のサプライズ。
まっ黄色の大銀杏と真っ赤な楓も見事でしたが、昨年開館した「宝物館」の「長谷川等伯の国宝絵画」に目を奪われました。「雪松図」、「桜図(久蔵)」「楓図」、「松に秋草図」、「松に黄蜀葵図」、「松に立ち葵図」の6点は全て国宝です。

こんな小さな姿でも富士山には元気が貰えます、電車から見えると
(編集子)大田区立赤松小学校昭和26年卒6年2組。戦後の混乱はようやく一段落したものの、朝鮮動乱が始まり、新たな世界が始まったころ、遊び場はまだ焼け跡で(ここでよく 匂いガラス なんてものを探したもんだ。B29の窓ガラスの破片だ、なんていう説があって見つけると宝物みたいにしたりしたのを思い出す)、今は見かけることもないが ”コッペパン” に甘いだけの安ジャムがのっている、それだけで大ご馳走になり、北千束と大岡山の子供料金が50銭だった、そういう時代だった。GHQ(占領軍司令部)の押しつけ改革にあおられて教育現場にも混乱が絶えなかったあのころ、戦線から帰国し、新時代には新しい教育が必要と信じて教員免許を取ったひとりの熱血青年が僕らのクラスの仲間を育てた。旧態依然の古手教師とは子供たちとの向き合い方をめぐって真っ向から張り合い、噂では殴り合いも辞さなかったという ”会津っぽ” そのものの人、今の世の中にこそ求められる、まさに僕らの 恩師 と呼ぶにふさわしい人だった。その教え子たる僕ら2組はいまだに ”クラス仲間” と誇れる友情を保ち続けている。
そのクラス仲間の一人の筆者は小柄で、すばしこくて、ほがらかで、男の子だったらさしずめ 弾丸小僧なんて呼ばれていたかもしれない少女だった。彼女をはじめとして、お互い米寿をうかがう年齢になっても続いている小学校クラス会、というのは調べたことはないが慶応幼稚舎みたいな特例は別として、あまりないのではないか。春になったらまた誰かが言い出して集まることになるだろう。
 無法の地となった町を自らの手で一変させようとするロイ・ビーン
無法の地となった町を自らの手で一変させようとするロイ・ビーン
冒頭テキサスのペコス川は文明の境界線で、川より西は法も秩序も
これからは、暴力的なのに、何処か滑稽な個々のエピソードの積み
まう。それから20年、石油王となったガスは自分に盾突く者は撃
ポール・ニューマンが西部の実在した人物を演じた映画は他に、ビ
*********************************************
①恋人までの距離(Before Sunrise)’95 (米)
アメリカからの旅行者ジェリー(イーサン·ホーク)は、
 2作目はパリを背景に、
2作目はパリを背景に、
河瀬さん
2019年6~7月の旅行は、もうあまり行けないのでは…と思い、最初と最後は私のいきたかった所、 中に主人の希望する場所を訪れました。 ミラノ、フィレンツェを訪れ、トリノで車を借り、クールマイユール、シャモニー、セントバーナード峠を越え、 チェルビニアへ、 そして最後は私の希望したイタリアのマッジョーレ湖で少し長い2 5日間の旅を終えました。 河瀬さんが歩かれ、主人がエギーユ・デュ・ミディから滑った(ガイド付き)という、 モンブラン氷河の雪は写真のように消えていました。 またチェルビニア(広場からの写真)は利用はスキーシーズンのようで、 借りた広いコンドミニアムは人の気配があまりなく、 ホーンテッドマンション状態でした。 *先日送られてきたJCBの旅の冊子の“大特集“は「今年のクリスマスはヨーロッパで」。 好きなホットワインを飲みながら、パリやドイツ、オーストリアのおとぎの世界のような写真を眺めて我慢します。 寒そうですし。 プレスリーの《Xmasは我が家で》(I’ll be Home forChristmas)を聴きながら…。小田篤子