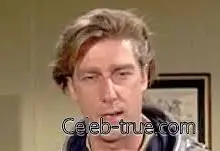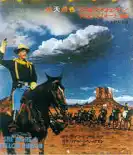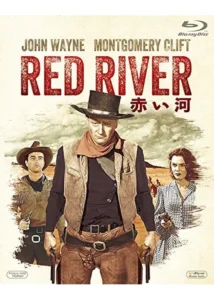(話の始まり)
(41 斎藤孝ブログ記事)
………..夕食の献立の話だった。三匹の若鮎を買ってきた。天然物は高いので養殖物で我慢した。大型のよく肥えた鮎だった。こんがりと炭火焼にする。子供の頃、72年前に富山の神通川で友釣りしたことを懐かしんだ。
おとりの鮎は買ったものだった。生きているから慎重に尾に針を付けた。おとりのメス鮎に若鮎が群がってくる。恋の縄張り根性を熟知した鮎の釣り方。流れも速いからなかなか難しい。竿さばきをすること1時間。竿がしなり重くなった。釣れたぞ~~~(唸る)
ぴちぴちした若鮎は友釣りに騙されたのだ。爺様宅で「鮎の塩焼き」にした。ほんのりと苦味ある若肌。美味かった。庭のギボウシは満開だ。そしてシュウカイドウも真っ赤な花を付けてくれた。
「鮎の塩焼き」から「愛の塩焼き」へと変わった。
(42 河瀬斌)15年前の夏に友人たちと立山観光と「おわら」を見にゆきました。その後五箇山に行った帰り、神通川沿いの「鮎や」という料理屋に入り、鮎を注文したところ、東京の様にたった一匹皿に乗っているのでなく、大皿に塩焼きした若鮎が山盛り出たのでびっくりしました(写真)。若鮎なので頭ごと食べたその美味しさが忘れられず、7年ほど前にその店を再度訪れましたが味は変わりませんでした。 その後自宅でも味わえるかと、取り寄せましたが、残念ながら焼きたての味とは比べ物になりませんでした。 カメさんはその近くの富山生まれですから、その店を知っているでしょうか?
 (斎藤)鮎や」は庄川峡の近くにあります。富山でなくて隣町、高岡の近くです。これも超有名な鮎料理。カメは残念ながら行ったことなし。河瀬さんは、お金持ちなので大皿の鮎の塩焼きを注文した。羨ましい。これこそ本物、天然鮎ですね。ただし神通川のものではありませんよ。
(斎藤)鮎や」は庄川峡の近くにあります。富山でなくて隣町、高岡の近くです。これも超有名な鮎料理。カメは残念ながら行ったことなし。河瀬さんは、お金持ちなので大皿の鮎の塩焼きを注文した。羨ましい。これこそ本物、天然鮎ですね。ただし神通川のものではありませんよ。
神通川は飛騨では高原川となり、その支流の蒲田川は笠ケ岳と槍ヶ岳を源流とする。余談ですが、富山市は神通川と常願寺川に挟まれています。常願寺川の源流は「称名の滝」。地鉄(富山地方鉄道)の有峰口から入ると、「亀谷温泉」があります。亀谷一族の発祥の地です。これこそカメの本当の故郷。「Turtule Valley」、先祖は地侍あるいは山賊だった。越中は戦国期に一向宗が多く、治めにくい。
前田家以前の佐々成政は大変苦労した。成政は称名の滝沿いに弥陀ヶ原に行き「一の越」を越えて信濃に逃げたそうです。成政にちなみ「サラサラ峠」ともいう。カメは小学校5年生まで富山市の爺様宅で暮らしたので、カメのルーツにこだわっていました。貧乏人の誇りは怪しげなルーツだけ。
カメの「鮎の塩焼き」は神通川のものであり亀谷の川で育ったものだけです。
(44 安田)聞くだけで、見るだけで涎が無意識に垂れるほどの美味しそうな鮎塩焼きです。羨ましい限り。岐阜県長良川の上流、”郡上おどり”で知られた郡上八幡を訪れたことがあり、簗で捕獲された新鮮な鮎を食したことが一度ありました。もう味を覚えていませんが、絶品だった記憶は残っています。
(42 下村)カメさん、安田さん、河瀬さん。 皆さん趣味というか興味の世界が広いというか、とにかく多彩。 絶対ボケませんね。
(36 浅海)お2人の言葉遊びについて行くつもりはありませんが河瀬さんの「鮎や」の若鮎塩焼の大皿盛りいかにも旨そうだなあ。是非鮎やに行ってみたいと思えてなりません。こんな鮎の塩焼の大皿盛り今でもいただけるのかな。是非神通川行きを考えます。
大昔琵琶湖の北西岸に注ぐ確か広瀬川とか言う川で釣りたての若鮎を嫌というほど沢山食べさせてもらった記憶がありますが鮎やのように 旨そうだなあ、冷で一杯飲みたいなあ と思う「鮎の塩焼き」ではりませんでした。鮎やに負けない美味しい鮎の塩焼きを食べさせる店近場に無いかなあ。。。
(編集子)下村君の感想に同調。日本って平和な国だよなあ。
*****************************
ウイキペディアにいわく:
神通川は、その源を岐阜県高山市の川上岳(標高1,626m)に発し、岐阜県内では宮川と呼ばれ、川上川、大八賀川、小鳥川等を合わせて北流し、岐阜、富山県境で高原(たかはら)川を合わせ、富山県に入り神通川と名称を改め、神通峡を流下し、平野部に出て、井田川、熊野川を合わせて日本海に注ぐ、幹川流路延長120km、流域面積2,720km2の一級河川です。
神通川流域は、富山、岐阜両県にまたがり、富山県の県都である富山市、南砺市、岐阜県の高山市、飛騨市の4市からなっています。
沿川及び氾濫域には、平成27年に開通した北陸新幹線をはじめ、あいの風とやま鉄道、JR高山本線、北陸自動車道、東海北陸自動車道、一般国道8号、41号等や国際空港の富山空港及び国際拠点港湾の伏木富山港(富山港)の基幹交通ネットワークが整備され、中部縦貫自動車道が整備中である等、交通の要衝となっています。また、富山平野では水稲の生産が盛んなほか、都市基盤の再構築が進む富山市街地や国内外の観光客で賑わう飛騨高山を擁し、富山城や高山の古い町並み、越中八尾のおわら等の歴史的・文化的資源にも恵まれ、古くからこの地域の社会・経済・文化の基盤を成しています。さらに、豊かな水の流れを利用した水力発電地帯としても知られており、中部山岳国立公園、宇津江四十八滝県立自然公園や神通峡県定公園等の優れた自然環境が数多く残されています。
(もうひとつの 神通 のこと)
昭和17年(1942)7月2日、アメリカ軍はソロモン諸島を足がかりとした反抗作戦を発動。8月7日に大挙ガダルカナル島に上陸し、その後約半年に渡る死闘を演じた。ガダルカナル島をめぐる死闘に終止符が打たれた後、戦場はソロモン諸島西部へと移った。 これに対し日本軍は、航空機と水雷戦隊による反撃を行った。そして5日の夜には兵員2400名、物資約180tを載せた7隻の駆逐艦と支援の駆逐艦3隻が、ニュージョージア島の北西に浮かぶコロンバンガラ島に向

かった。 7月12日22時35分、米海軍36.1任務群の索敵機が日本艦隊を発見。
日本側の布陣は旗艦が軽巡「神通(じんつう)」、それに駆逐艦「清波(きよなみ)」「三日月」「浜風」「雪風」「夕暮」、輸送隊として駆逐艦「皐月(さつき)」「水無月(みなづき)」「夕凪」「松風」が参加、というものであった。
戦いが始まってすぐ、サーチライトによる照準射撃を行っていた旗艦神通が集中放火を浴び、艦橋に砲弾が直撃して司令官の伊崎少将が戦死する。それでも神通は主砲を撃ち続け、7本の魚雷も発射。ところが米駆逐艦が放った魚雷が命中し、船体が真っ二つに分断された。後部は瞬時に沈んだが、前部は沈まなかったので、残された一番砲塔のみで戦い続けた。
開始直後に集中攻撃を受け、大爆発を起こしつつも船体前部のみで2時間以上も戦い続けた神通の最期は、どんなものであったか誰も知らない。早朝に駆逐艦皐月と水無月が捜索に向かったが、艦影はおろか一人の生存者も発見できなかったのである。