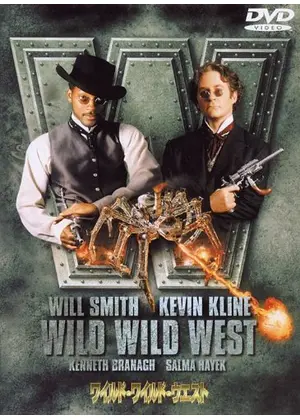(編集子)僕が ブログ というものに興味を持ったのは、自分の人生航路でたびたび起きていることなのだが、全くの偶然というか、いきあたりばったりのことがきっかけだった。例の通り、ぶらりと入った本屋で、島田君が書いているワードプレスというツールについての入門書(文末参照)に出合ったからだ(注:”ブログ” と ”ホームページ” は運営方法や目的はちがうが実質的には同じものと考えてよい)。
僕が三田を卒業したころ、社会では事務合理化、という流れが起きていて、先進的な企業ではコンピュータの導入がはじまりつつあった。就職した横河電機もその一つで、新人を採用してその中から ”コンピュータ屋” を自家生産しはじめたタイミングにたまたまボクが採用され、何も知らないうちにコンピュータの世界に放り込まれたことが結果的に僕のサラリーマン生活を決定づけてしまった。いろんな仕事をさせてもらったが、退職後10年たち、サンデー毎日生活にも飽きがきはじめたころ(ボケ防止にハードボイルドミステリのほかにもうひとつ、なんか新しいことがないかなあ)と思い始めた、ちょうどそんなタイミングで島田君のいっている入門書に出合ったというわけだ。
僕が実際にプログラムにかかわっていたころはまだCOBOLもうわさに聞く程度のものでアセンブラが常識だったし、”外部記憶” といえばディスクなんてものは1台のレンタルが数十万円とべらぼうで、普通は磁気テープ、という時代、横河電機(当時のことだ、無論)半年間の受注統計、なんていうとデータのソート(ならべかえ、分類)だけで徹夜しなければならない、そんな時代だった。そういう時代の感覚で行くと、島田君が書いている オープンシステム なんてものは夢想もしないものだった。だからワードプレス、というしかけを本屋で買った本1冊の知識で動かす、という事は、いわば快晴無風、新雪の斜面にシュプールをかくような、またとなくスリリングであり、わくわくすることだった。
いまの時点で島田君の投稿を得て、あらためて、(ああ、そういうことか)と思い当たることばかりだ。あと何年、自分に残された時間があるのかわからないが、高尾山歩きも早晩、あきらめなければならないかと思い始めた今、ブログつくりはまたとないスリルと多くの友人たちとのつながり(これこそ認知症予防に最高のものだというドクター篠原の忠告をきいたばかりだ)を与えてくれている。本稿の内容は多少、専門的な部分を含んでいるのでとっつきにくいとは思うのだが、僕につづいてこの世界に入ってみようか、という仲間が現れるのを楽しみに待っている。
******************************
(島田) 同期の友人の誘いのもと、退職後で暇な時間を持て余していた時、WordPressでホームページ(HP)を作る機会を与えられた。元々、企業内の基幹システムをWEBで開発した経験は持っていたが、これ程、オープンな世界で仕組みを構築できる経験は初めてであった。企業内のシステムはJava等のオープンな技術を使っているが、セキュリティ上の関係で、クローズな考え方(他の人に推測されない)で作られている。この世界から外に出ると今までとはまったく異なるオープンな世界が広がっていた。
WordPressはグローバルでも日本でもシェア約50%を持つ、HP作成ツールである。別名、CMS(コンテンツマネージメントシステム)とも言う。WEBのテキスト・画像・デザインを一元管理するツールの事を指す。書店でHP関係の本棚を探すと、50%以上はWordPressに関する本が並べられている。このツールを利用して個人のブログから企業のHPまで様々な形で利用されている。そしてオープンソースのため、ただで利用することができる。お金をかけないで、趣味の世界で、非営利で情報共有の場を持つ場合、最適のツールと言って良い。ちなみに、このサイトもWordPressで作られている。
HPを運営するためにはHP作成ツールだけではサービスを提供できない。HP環境を維持するためのサーバが必要である。現在、このサーバを提供しているレンタルサーバ会社が多数あり、低価格(年間1万円程度)でサービスを提供している会社が人気となっている。この価格であれば、個人でも充分運営できる。また、このサービス内で独自ドメイン(~@~)を設定したり、WordPressのQAをしたり、バックアップを自動で作成したりとサービスも充実している。また、WordPressの開発環境も簡単に作成することができる。
WordPressの開発環境ではダッシュボードと言う管理画面があり、テーマ(外観)の選定、メディア(文書ファイル、写真等)の管理、投稿・固定ページ(HP画面イメージ)の作成、プラグイン(追加機能)の選定ができる。テーマとはHPのデザインや機能を追加で提供するもので、1つのみ選定することができ、一括してWordPressのデザイン画面の強化が図れる。登録されているテーマは1万以上あり、誰でもが参加できるオープンソースのなせる業である。同様にプラグインも5万以上あり、これは複数選定でき、こんな機能が追加でほしいと思うような機能が提供されている。投稿・固定ページの作成ではブロックエディタという機能が提供されており、今までにバージョンアップが繰り返され、かなり使い勝手が良いものとなっている。テーマ・プラグインには無償・有償のものがあるが、特殊なことをやらなければ、無償で充分である。WordPressはサービスの提供する側と受ける側がWin-Winの関係で、大量ユーザに安いサービスの提供が実現できている。
そして、システム開発屋にとってうれしいことはWordPressがオープンソースのPHP(プログラミング言語)とオープンソースのMySQL(DB管理ソフト)で開発されていることだ。元々、HPはHTML(マークアップ言語)とCSS(ページのスタイル(文字の大きさやフォント等)定義)で作成されていた。ところが、HPの利用拡大と高度化のニーズにより、HP作成言語としてPHPが利用されるようになった。PHPはHTML(静的言語)に動き(データ処理等)を加えた言語で、オブジェクト指向の機能を持ち、それでいて比較的習得しやすい。このため、WEB系の基幹システムの開発でも機能豊富だが習得が難しいJava(プログラミング言語のひとつ)に代わって、利用されるケースもでてきている。
WordPressではPHPのソース内容、MySQLの定義内容が公開されており、PHPを勉強する上では最適の環境が提供されている。Javaツールを利用した基幹システムのスクラッチ開発に長年携わってきた私にとって、Javaプログラミングの習得は長年の課題であったが、いまだにプログラミング前の工程の仕様作成で止まっている。PHPはプログラミング再挑戦のきっかけになるかもしれない。これができれば、プラグインの独自開発も夢ではない。なかなか面白い世界である。
WordPressの立ち上げに約半年携わっているが、 その中で思ったことはWEB上での情報量の多さ。何かわからないことがあるとWEB検索ですべて解決することができる。自分が困っていることは他の人も困っているのだなと実感できる。これがオープンの世界かと…
まだ、WordPressというオープンの世界には足を踏み入れたばかりであるが、HPの機能拡張も含め、この世界は奥深く、わくわく感を持って、今後も携わっていきたい。
*******************************

(別に宣伝をしているわけではないが、現在の小生のブログはこの本1冊だけを頼りに作られている ― もちろん、幾度もコージこと菅井康二君のヘルプをもらってのことだが。別の言い方をすれば、日本語が読めて、Eメールが一応使えて、もひとつ、MSワードの基本がわかっている、という程度の知識があれば、エラソーに言っているが ”ジャイさんのブログ” 程度のことは誰でもできる、ということだ。 やってみないか?)