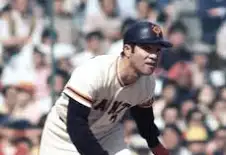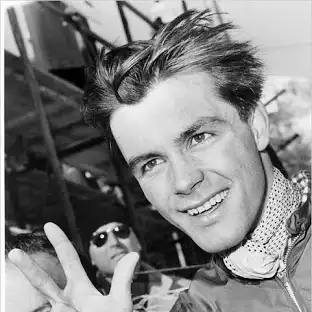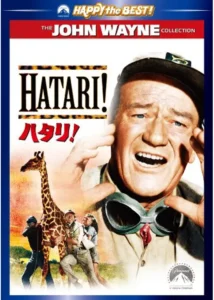そもそもの話:
(中司)新聞にセリーグの個人タイトルが載っています。
(菅原)Wikipediaによると、1967年、赤手袋の柴田勲の盗塁は70!大谷も顔色なし。
(下村)小生、野球中継はまったく見ませんが「球辞苑」という番組はよく見ています。素人にはこれがとても面白い。この番組によると野球選手は頭が良くないと務まらないということがよくわかります。対戦相手の全選手のクセやどのような時にどのような動きをするかなどを記憶する力、相手の心理状態を読み取る推理力など。 囲碁や将棋の棋士は対戦したときの布石などをすべて覚えていると聞きますが、これとまったく同じなのですね。
昨日は大谷の完敗、ダルビッシュの完勝でしたが、ニュースでも紹介されていた通り、ダルビッシュは投球ごとに投げる球種はもちろん、間合いの取り方、球速の緩急などありとあらゆることに頭脳を巡らせて投球していたとのことです。
過去の「球辞苑」によると、例えば3ボール・2トライクでフルカウントになったときにどのような球を投げるか。対する打者の過去のフルカウント時の対応を思い起こして球種や球速を決めていると。「球辞苑」ではこれをキャッチャー場合、併殺を狙う場合のショートやセカンドの場合、併殺されそうになった選手の場合など各球団の各選手のノウハウが披露されており、過去の数値データとつき合わせながら紹介されています。もっとも企業秘密的なこともありますから、すべての手の内を晒すようなしゃべりはないでしょうが・・・。
因みにかつて100mを10秒台で走る陸上選手をピンチランナーに起用したことがありましたが、ある解説者は早く走れるだけではダメだ、陸上競技は「用意、スタート」のシグナルがあるからスタートを切るのは簡単、野球では投手のクセや投球フォームなどを頭に入れて自分でスタート時点を決めなくてはならないから難しさがまったく違うと。野球も奥が深いですね。
 (保屋野)貴兄から野球談議が聞けるとは・・・幅広い関心に感心。盗塁に関して、改めてネットで調べました。メジャーでは、リッキー・ヘンダーソンが1406でトップ(シーズンでは130で2位。1位は1887年ニコルの138)日本では福本の1065がトップ(シーズンでも106とトップ)
(保屋野)貴兄から野球談議が聞けるとは・・・幅広い関心に感心。盗塁に関して、改めてネットで調べました。メジャーでは、リッキー・ヘンダーソンが1406でトップ(シーズンでは130で2位。1位は1887年ニコルの138)日本では福本の1065がトップ(シーズンでも106とトップ)
日本のプロ野球は、盗塁はもちろんですが、ホームランも少なく、非力なバッターが目立ちます。大昔の、西鉄「豊田・大下・中西」、巨人「王・長嶋」、阪神「バース・掛布」の時代が懐かしい。このままだと、第二の(魅力ない)「男子ゴルフ」となってしまうのでは。なお、シモさんの「100m10秒台の選手」とは飯島のことだと思いますが、確かに100mを10秒で走る彼が成功しなかったのが不思議です。
(安田)近本以前の盗塁王最低盗塁数は、
大リーグの昨年辺りの規約変更も盗塁数の増加に関係していると、数カ月前にテレビで解説を見た記憶があります。ピッチャーが投球までの15秒以内のピッチロック、牽制球は2回まで、それと塁ベースのサイズが少し大きくなったこと。この3つ共にランナーには有利に働いているようです。
塁ベースのサイズが大きくなれば、塁間の距離も若干とは言え短くなる上に、塁に身体が触れる面積も広くなるので走りやすいのでは・・。イチロー選手が現在大リーグで活躍していたら、多分、大谷選手にシーズン盗塁数の日本人記録は破られず、もっと記録を延ばせたのではとも思います。