 英国の探偵小説作家、アントニー・バークリーの「最上階の殺人」(原題:Top Storey Murder。翻訳者:藤村裕美、発行:1931年)、「地下室の殺人」(原題:Murder in the Basement。訳者:佐藤弓生、発行:1932年)を読む。いずれも、創元推理文庫。
英国の探偵小説作家、アントニー・バークリーの「最上階の殺人」(原題:Top Storey Murder。翻訳者:藤村裕美、発行:1931年)、「地下室の殺人」(原題:Murder in the Basement。訳者:佐藤弓生、発行:1932年)を読む。いずれも、創元推理文庫。
先ず、バークリーについて簡単に触れておこう。バークリーの本名はA.B.コックス(代表作は、「黒猫になった教授」)だが、他にフランシス・アイルズ(「レディに捧げる殺人物語」。これは、A.ヒッチコックが監督した映画「断崖」の原作)、A.マンモス・プラッツ(「シシリーは消えた」)名義の筆名がある。そのバークリーは、1893年生で、1971年に死去し、例えば、A.クリスティーは、1890年生で、1976年に死去しているから、この二人は、ほぼ同世代であり、所謂、英国の本格探偵小説黄金時代を築いた作家と言うことになる。
本格探偵小説とは、端折って言ってしまえば、殺人が起こり、その犯人を捜すべく、警察、私立探偵が行動を起こし、最後に犯人を逮捕する。しかし、小説だから、その全権は作家が完全に握っており、作家はあの手この手を使って、例えば、ミス・ディクレクション(作家が読者を間違った方向に誘導する)などで、読者を幻惑し、最後まで読者から犯人を秘匿する。犯人が捕まったとしても、最後まで真犯人を秘匿することが出来れば、その作品は高く評価されることになる。だから、探偵小説の出来具合は、作家がその真実について、読者を最後の最後まで如何に騙しおおせるかと言う、それこそ作家の手腕如何に掛かって来るわけだ。
「最上階の殺人」だが、ロンドンの閑静な住宅街、四階建てフラットの最上階で女性の絞殺死体が発見されるところから話しは始まる。現場の状況から警察(スコットランド・ヤードのモーズビー主席警部)は物盗の犯行と断定するが、一方、捜査に同行していた作家のロジャー・シェリンガムは、同じフラットの住人による巧妙な計画殺人と推理する。ここから話しは、専ら、その中に容疑者がいるであろうと思われる住人全員の聞き込みをするシェリンガムを中心に展開され、モーズビーは時たま顔を覗かせる程度だ。従って、読者は(小生も)、シェリンガムに完全に感情移入してしまい、何とか早く犯人を見つけてくれないものかと念ずるばかりとなる。しかし、これは、実は、バークリーが仕掛けた壮大なミス・ディレクション(作家が読者を間違った方向に誘導する)であって、真実はここにはない。
「地下室の殺人」は、新居に越して来た新婚夫婦が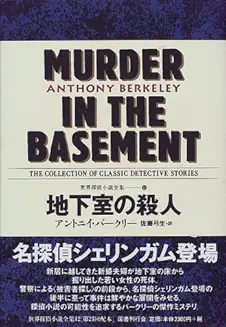 その地下室で掘り出したのが、若い女性の腐乱死体だったことから話しは始まる。しかし、被害者の身元が分からぬことから、上記、モーズビー主席警部は、その身元を詳らかにするために、警察小説であるかのように極めて地道な捜査を展開する。唯一の手掛かりは、被害者が、右の大腿骨を骨折し、その為にプレイトによる治療を受けた女性であることが判明し、その身元調査が行われ、最後の一人が、偶々、上記のシェリンガムが一時期代用教員を務めたことのある学校の教員であったことから、シェリンガムも捜査に乗り出すこととなる。ここで、作家、シェリンガムの代用教員時代の学校の話しが、作中作として披露され、学校内の複雑な人間模様が浮き彫りとなる(これが、なかなか面白い)。被害者が判明し、モーズリーは、その犯人が誰であるか薄々分かって来たが、徹底的な証拠を見い出すことが出来ず、シェリンガムに援助を仰ぐ。最後は、シェリンガムが、全く意外な人物を犯人と断定する。
その地下室で掘り出したのが、若い女性の腐乱死体だったことから話しは始まる。しかし、被害者の身元が分からぬことから、上記、モーズビー主席警部は、その身元を詳らかにするために、警察小説であるかのように極めて地道な捜査を展開する。唯一の手掛かりは、被害者が、右の大腿骨を骨折し、その為にプレイトによる治療を受けた女性であることが判明し、その身元調査が行われ、最後の一人が、偶々、上記のシェリンガムが一時期代用教員を務めたことのある学校の教員であったことから、シェリンガムも捜査に乗り出すこととなる。ここで、作家、シェリンガムの代用教員時代の学校の話しが、作中作として披露され、学校内の複雑な人間模様が浮き彫りとなる(これが、なかなか面白い)。被害者が判明し、モーズリーは、その犯人が誰であるか薄々分かって来たが、徹底的な証拠を見い出すことが出来ず、シェリンガムに援助を仰ぐ。最後は、シェリンガムが、全く意外な人物を犯人と断定する。
これで、シェリンガムとモーズリーの直接対決は、ここでは1勝1敗、互角の勝負となったが、例え、名探偵と言われるシェリンガムと言えども間違えることがあると言うことなのだろう。例えば、クリスティーのH.ポワロにしてもJ.マープルにしても、間違えることは絶対になかったのではないか。この辺が、同じ黄金時代を過ごした二人ではあるが、バークリーの独自性が際立っている。
最後に、いずれの作品についても、ボンクラな小生、犯人を割り出すことは出来なかったが、一部の識者が大傑作のように褒めたたえているのにはただただ違和感を覚えた。
(編集子)スガチューの言う通り、世の中のエキスパートとか評論家という人種 のセンスは理解しがたいものがある。どっちへ転んだって、要はエンタテインメントなんだから、読んだ本人が面白ければ、それが(少なくともミステリの世界では)傑作なんだと思っている。この2作は小生未読だが、今日時点でいえば、小生が感嘆したのは(実はこの連休に読破する予定だったがまだあと11ページ残っている)、コーネル・ウールリッチのPhantom Lady (翻訳題 幻の女)と、いわゆるエキスパートなら鼻で笑うだろうがクリスティのアクロイド殺人事件で、最後は思わず本を取り落とす(いいすぎかな)ほどのショックを受けたものだった。友人諸君、ミステリの門を叩きたまえ。鬱屈の気分が和らぐぜ。
のセンスは理解しがたいものがある。どっちへ転んだって、要はエンタテインメントなんだから、読んだ本人が面白ければ、それが(少なくともミステリの世界では)傑作なんだと思っている。この2作は小生未読だが、今日時点でいえば、小生が感嘆したのは(実はこの連休に読破する予定だったがまだあと11ページ残っている)、コーネル・ウールリッチのPhantom Lady (翻訳題 幻の女)と、いわゆるエキスパートなら鼻で笑うだろうがクリスティのアクロイド殺人事件で、最後は思わず本を取り落とす(いいすぎかな)ほどのショックを受けたものだった。友人諸君、ミステリの門を叩きたまえ。鬱屈の気分が和らぐぜ。
